ZOZOに勝つ!日本のアパレルが「シーイン」になる唯一の手法とは
いまからZOZOに勝つデータベースを作ることは不可能
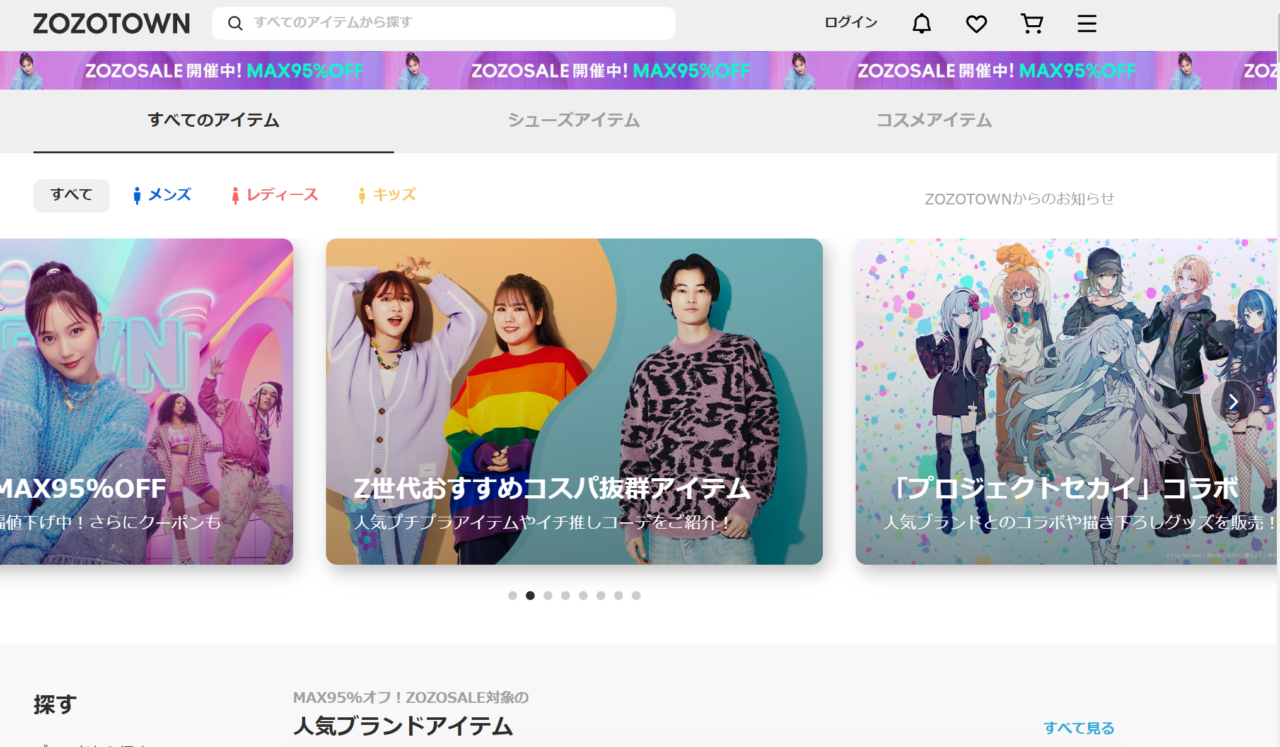
また、そのブランドの服しか買わないという顧客の割合である「服の顧客率」は、10代から40代まであまねく20%もない。ほとんどの人がある程度の幅をもって、複数のブランドをホッピングしている。「うちの顧客とZOZOの客は違う」などという人たちはどういう調査をしているのか。
いずれにせよ、ユニクロ快進撃、外資SPAの躍進、Z世代の中国・韓国アパレルの抱え込みに、外的要因としてSDGsによる「買い控え」が加わり、確実にアパレルマーケットはシュリンクしている。今、調子が良いのは過去例をみないほどの円安がつづき、「観光立国」をうたった岸田政権のインバウンド誘致とコロナの反動、いわゆるリベンジ消費のおかげだろう。大事なことは、PDCAというのは、負けているときだけにやるのでなく勝ったときこそ正しい投資を行い、「買った理由」を分析することが大事なのだが、日本企業は概して負けたときに慌てて、PDCAだと会議や承認を増やす。
こうして、今年の猛暑が再び襲ってくる夏あたり、日本のアパレルは在庫の読み違いによる大ダメージを受け、中国・韓国などアジア・アパレルの日本への本格参入が始まるというのが私の「読み」だ。この「デジタル x AI時代」には、SPAは負けるモデルなのである。デジタル x AIの時代は「無在庫マッチングモデル」(シーインのビジネスモデル)が勝利のモデルなのだ。
さて、こうして売上が下がった状況で無理に売上を取ろうとするとどんなことが起こるか。私が再三「循環経済下では、売上・利益の大きさは企業の強さを表すわけではない」といっているにも関わらず、下調べも準備もしていない状況の中で、唯一絶対的に売上が上がるのは「ZOZOTOWNへの出店」ということになる。そして、日本人の10人に1人がアクティブ会員だという事実にもかかわらず、御用コンサルに「顧客が違う」など、意味不明なロジックをつくらせ、自分の顧客を差し出す(ZOZOTOWNへ出店する)わけだ。
私は通販企業で取締役やコンサルを6年やっているから、一旦自社サーバに顧客情報を入れたら、通販企業は全精力を集中し、その顧客を絶対に逃さない。アップセル、クロスセルで売上を上げるなど、あの手、この手でLTV (顧客生涯価値)を長期化させてゆく。いまだに、日本のアパレルの事業KPIは、商品ベース(商品回転率、商品粗利、交差比率など)で顧客ベース(CPA/LTVなど)ではない。ボケッと商品ベースのKPIを追いかけている間に、顧客ベースの管理会計を導入している競合にしてやられるのである。
それでは、我々はZOZOを無視できるのかという疑問にたどり着くが、残念ながら、時既に遅しである。よほど差別化できる戦略を実践できなければ、売上面で大きなダメージを受けることになる。なにぜ、日本人の10人に1人だ。よく考えていただきたい。ZOZOは在庫リスクも持っていない。在庫リスクはテナント側が持つ。また、AIをつかったクロスセルや、よりコスパのよい類似商品へのリプレイスもZOZOがイニシアティブを持っている一方、値下げやポイントはテナント側の負担になる。ZOZOにとってよいことばかりなのである。このように、「優良顧客」をしっかり抱え込んでいる企業は、売上がある臨界点を超えたら勝ちサイクルに入ってゆき、誰も止められなくなる。テナント側はほとんど使えないマーケティングデータが見えるだけで、ZOZO店舗内での自由度もほとんどない。
それならば、このZOZOモデルを他のアパレルがやればよいではないかと素人はいうだろう。しかし、日本人に10人に1人というアクティブユーザを抱えるZOZOに勝つデータベースを今からつくるのは不可能だ。
では、どうすればよいのか? そこで出てくるのが「シーイン・モデル」だ
河合拓のアパレル改造論2024 の新着記事
-
2025/03/19
日本人の服がこの10年で「ペラペラ」になった本当の理由_過去反響シリーズ -
2025/03/12
ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ -
2025/02/18
ユニクロと競争せず“正しい”戦略ポジションを取っているアパレルとは -
2025/02/11
「あえて着ない」人が増加中 スーツ業界の復活はあるのか? -
2025/02/04
参入多いが難しいアパレルの多角化戦略、成功の秘訣は? -
2025/01/28
正しいTOC(制約理論)の理解 余剰在庫と欠品が激減する本当の理由!
この連載の一覧はこちら [61記事]
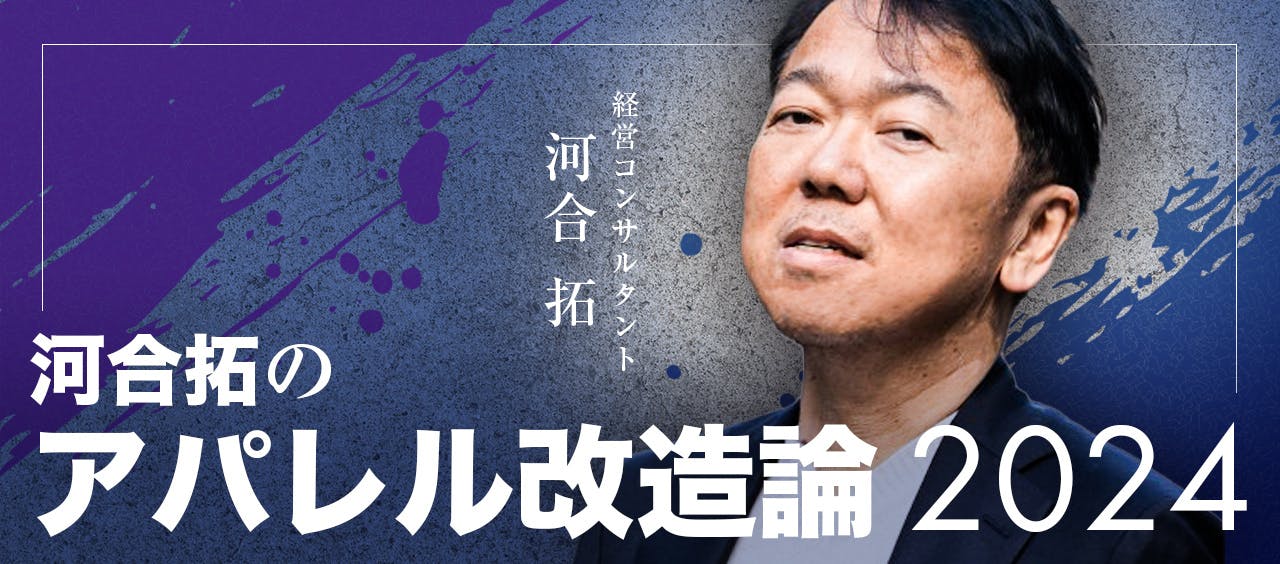
ファーストリテイリング(ユニクロ),しまむらの記事ランキング
- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ
- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは
- 2022-04-15鈴木誠社長が語る、しまむらがコロナ禍でも業績好調の理由とは
- 2025-11-04ユニクロの「棚割り」に見るインクルーシブMDへの“覚悟”
- 2021-03-05ビジネスは「一勝九敗」 ファーストリテイリングを世界的大企業に導いた“柳井哲学”
- 2022-11-29シーイン模倣騒動と大差ないアパレル業界のパクリ体質 シーインがそれでも勝つ理由
- 2025-09-30しまむら高橋新社長がめざす、 ”しまむら偏重”からの脱却の道筋
- 2021-05-11キーワードは科学、製販統合!「無敵のユニクロ」を凌駕する「知る人ぞ知る」ファッション商品
- 2023-08-28ユニクロと東レとのサステナブルな関係から生まれたリサイクルダウン
- 2023-11-14GMS衣料のジレンマと真実!イトーヨーカ堂アパレル完全撤退の必然とは
関連記事ランキング
- 2025-11-25ワコールを追い詰めた「三つの革命」
- 2025-12-02HUMAN MADE上場から考えるファッション産業の構造的限界
- 2025-11-27急拡大するリカバリーウエア市場を攻略する
- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価
- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ
- 2025-11-24間違いだらけのアパレルDX改革、根本から変えるべき「KPIの設計哲学」
- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度
- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?
- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは
- 2022-04-22ユナイテッドアローズ重松理名誉会長が語る、創業秘話とビームスを立ち上げた理由とは
関連キーワードの記事を探す
国内ユニクロ事業が売上収益1兆円を突破 ファーストリテイリング本決算を徹底分析
アパレル売上ランキング2025 ファストリの売上高3兆円台に!
百貨店を生活商圏型SCに転換!「ららテラス川口」の全貌と戦略とは?





 前の記事
前の記事

