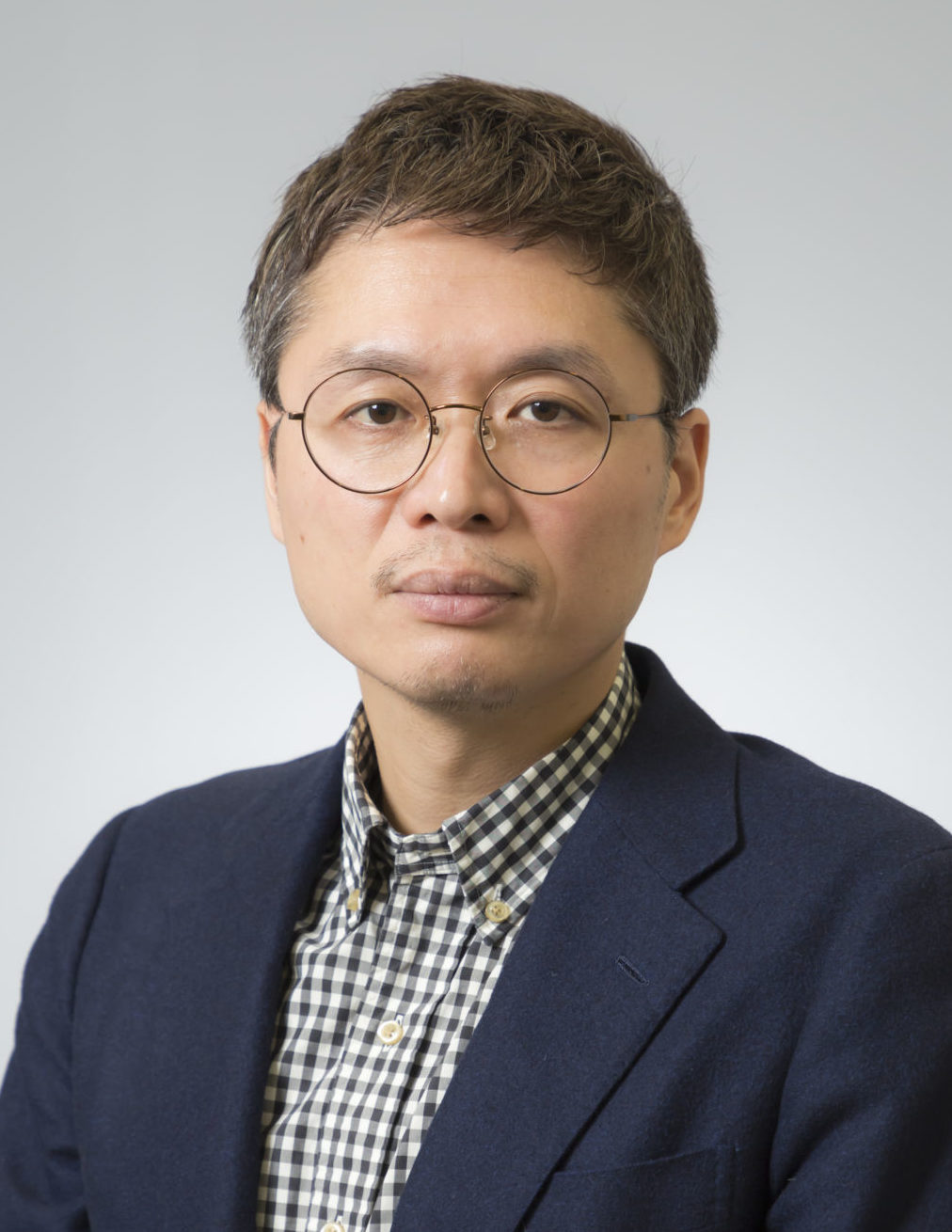三浦 弘社長が明かす、ビッグ・エーが小型家電や雑貨も品揃えしていく理由
イオン傘下で小型ディスカウントストアを展開するビッグ・エー(東京都)は、欧米で急伸している「ハードディスカウントストア」を長年ベンチマークしながら店舗開発を進めてきた。そして2019年10月の消費税増税を機に、日本でもハードディスカウントストアの存在感を高めたい考えだ。その戦略を三浦弘社長に聞いた。
ハードディスカウントストアが浸透しないのは認知度が低いから
──ハードディスカウントストア企業のアルディ(Aldi)やリドル(Lidl)を長年研究されています。

三浦 徹底したローコスト運営の手法を学ぶべく毎年、店舗を視察しています。とくに2社は近年、英国でのシェアを大きく伸ばしています。しかし英国でもかつては「アルディやリドルで購入した食材でつくった弁当を子供が持っていくと学校で恥ずかしい思いをする」と揶揄されていたこともあるほど、ハードディスカウントストア業態は軽視されていました。しかし2008年のリーマン・ショックや、11年の付加価値税の増税を好機に、消費者の支持を獲得していったのです。
日本では、ハードディスカウントストア業態と言える店で店舗数が100を超えているのは、「ビッグ・エー」と、同じくイオングループの「アコレ」(社名もアコレ、三浦弘社長が兼務)、関西圏を中心に店舗展開する「サンディ」の3つしかありません。10月の消費税増税をチャンスに「安かろう悪かろう」というイメージを払拭してハードディスカウントストア業態を浸透させたいと考えています。
──日本でハードディスカウントストア業態が浸透していない要因は何でしょうか。
三浦 認知度の低さではないでしょうか。一般的に食品スーパーの新店の売上高は、初年度に高い数値を出し、翌年以降は伸びても前年の102~103%で推移します。一方、「ビッグ・エー」の場合は、出店後5年くらいは売上高が前年の105~108%のペースで伸び続けます。認知度が徐々に高まりさえすれば、お客さまは繰り返し来店してくださるようになるのです。
現在、「ビッグ・エー」は首都圏に231店舗(19年6月現在)を展開しています。この規模では認知度を高めるのには不十分で、今後出店スピードを加速していきます。
競合7社の価格を調査「安さに根拠をつける」
──現在の消費環境をどう捉えますか。
三浦 すでにお客さまが業態で店を選ぶ時代ではなくなっています。SMやDSはもちろん、ドラッグストア(DgS)やコンビニエンスストア(CVS)などのすべての業態が競合となるなか、成長しているのは買い上げ点数を伸ばしている企業です。これを伸長させるために、当社では、HDSの最大の武器である「低価格」で競合他社と差をつけるべく「安さに根拠をつける」ということに力を注いでいます。
──具体的にどのようなことを実践されているのですか。
三浦 当社の商勢圏内で競合とするSM、DS、DgSの計7社の、プライベートブランドを含む共通の500品目の価格を、専任の担当者が毎週調査しています。そして、この500品目の合計金額が7社よりも20%以上安くなるように価格を設定しています。
ただ、500品目すべてを競合より20%安くしているわけではありません。当社では価格を設定する際に「安さ観」を意識しています。お客さまは、この金額以下なら安いと感じる「安さ観」を商品ごとにお持ちです。500品目の中でも、より訴求力の高い商品を、「安さ観」を圧倒的に下回る価格で提供することで低価格を訴求しています。
──「ビッグ・エー」の現在の基本的なフォーマットを教えてください。
三浦 売場面積は平均100坪です。ただ、今後都市部で出店攻勢をかけるためにより小型の店舗開発も進めており、70坪ほどのフォーマットも確立しつつあります。
ただ、売場面積は異なっても、設定する基本商圏は店舗から半径800mです。なぜなら、「ビッグ・エー」のお客さまの過半を占める50歳以上の方が、ふだんの買物のために移動される距離は片道800mほどだと考えているからです。この商圏内で「最も安い」と認知され、週に何度も利用してもらえる店になることをめざしています。
──取り扱うSKU(絶対単品)数についてはどのようにお考えですか。
三浦 全体で2400SKUほどが適正だと考えています。理由を説明すると、一般的な食品スーパーは売場面積600㎡ほどで約1万2000SKUを扱っています。マーケティングにおける「2:8の法則」のもと、売上上位2割の商品が全体の8割の売上をつくると想定し、食品スーパーの2割に当たる2400SKUを揃えれば、お客さまに必要最小限のコモディティ商品を提供できると考えています。
次のページは
わずか2400SKUに絞り込むのに、小型家電や雑貨を品揃えしていくねらい