ユニクロに負けずに利益を上げる!アパレル2024年「5つの論点」解決策とは
価格の安いユニクロ、しまむらに負けずに利益を上げる方法とは

次に論点4である。
論点4は、はじめから売れないことを前提に売れ残りや値引きを織り込んだ高額な値段をつけ、最終的に粗利率を60%程度とるか、値引きせずに売れる前提で前者の半額ほどの値段をつけ、最終的に粗利率を60%稼ぐかの違いだ。不況の日本経済下では後者が圧倒的に有利であり、しまむら、ユニクロ、ハニーズなどはみなこの方法をとっている、という話だった。
「ならば、同じことをすればよいではないか」というのは、あまりに安直である。なぜなら、いきなり価格を半額にすれば、それはもはや消費者にとって違うブランドとなるからだ。
ここで提案したいのは、最終価格を100%とすると30%が値引きか評価損・減なのだから、逆に考えてみるというものだ。
例えば、価値を高めるというのも検討しうる方法だ。例えば、ユニクロはカシミヤを1万円弱から1万2500円に価格を上げたり、他ブランドとのコラボレーションで、さらにデザイン料として値段をあげている。
ディスカウンターは、これまで低価格で売ってきたため、なかなか値段を上げつらい。しかし高価格帯のブランドが、そのブランドを「プライス・アンブレラ」(価格基準値)としてお手頃商品、つまり絶対価格は高いが、価値はそれ以上に高いものをつくる、ということである。
例えば、ユニクロはウールのエクストラファインの梳毛セーターを3000円前後で売っているが、これを肉厚にして5000円で売るという戦略だ。ユニクロのエクストラファインは薄く、おそらく150 ~ 200gぐらいと思われるが、これを250gぐらいの目付で、5000円で売るわけである。上代を下げられないなら、コストを上げることで同じコスパを実現するという戦略だ。
くどいようだが、ディスカウンターの価格が安いのは損益分岐点が低いからではない。「値付けに歩留まり分を織り込んでいるのかいないのか」という点が違うのである。だから、冒頭に上げたD2Cとあわせて、コストを上げれば論理的にいって利益率は増えるはずだ。コンサルという職業上、実際のアパレルの名前を挙げられないのが無念だが、実際に最近手伝った高価格ブランドは、欠品だらけではあるものの、値下げをせず(歩留まり分を価格に転嫁していない)に、プロパー消化率は80%を超えていた。また、上にあげたディスカウンターのプロパー消化率も、あまねく80%を超えている。
これも、実際の訴求価値をどこにおくかはご自身で考えてもらいたい。もちろん、私と一緒に考えてくださるという方がいらっしゃれば、いつでも飛んで行く。これが、私の回答である。
論点5SDGsの“残念な”解決策とは
最後に論点5のSDGsである。
これは、はっきりいって国の責任であり、個社でどうにかできる話ではない。例えば、バングラデッシュでおきたラナプラザ倒壊事件について考えてみよう。日本には建築基準法があり、また、義務教育制度がある。私たち日本人はこうした国が定めた法規制の中で生活しているわけだ。だから、その基準にしたがって建物を建てるし、未就学児童がいないよう義務として教育を受けなければならないわけだ。これを、倫理や「ひどいことするな」というような感情論で閉じ込めようというところに無理がある。
これについて「ファストファッション企業など製造を委託していた大手アパレルの責任である」と断じるのは、間違ってはいないがシステム、仕組みとしては不十分だ。これは、国が国に対して言うべき産業政策とも言えるもので、一企業がどうにかできる問題ではない。
いわば、企業はアクセル。法規制がブレーキの役割を果たして我々人類を正しい方向へ導いてもらわなければならない。例えば、タンパク質のような、何度も再生可能な繊維を使う場合、輸入税を免除するなどである。そうやって、経済合理性と企業の進むべき方向を官民が歩調をとりあってゆくべきなのだ。
すでに、フランスでは、洋服を捨てるとペナルティが科せられるなど、「国」がSDGsに介入している。私は、2年前からずっと同じことを言っているのだが、日本政府は放置プレイを続けている。SDGsはスーパーブランドにとって、ブランドエクイティ(ブランド価値を形成するもの)だが、一般アパレルにとってしてみれば、コストでしかないということをまずはしっかり合意することである。
「神の見えざる手」では、今後マスボリュームを形成するであろう超低価格アパレルに対して、SDGsが通用することはない。
河合拓氏の新刊、大好評発売中!
「知らなきゃいけないアパレルの話 ユニクロ、ZARA、シーイン新3極時代がくる!」
話題騒然のシーインの強さの秘密を解き明かす!!なぜ多くのアパレルは青色吐息でユニクロだけが盤石の世界一であり続けるのか!?誰も書かなかった不都合な真実と逆転戦略を明かす、新時代の羅針盤!
プロフィール

株式会社FRI & Company ltd..代表 Arthur D Little Japan, Kurt Salmon US inc, Accenture stratgy, 日本IBMのパートナー等、世界企業のマネジメントを歴任。
著作:アパレル三部作「ブランドで競争する技術」「
筆者へのコンタクト
https://takukawai.com/contact/
河合拓のアパレル改造論2024 の新着記事
-
2025/03/19
日本人の服がこの10年で「ペラペラ」になった本当の理由_過去反響シリーズ -
2025/03/12
ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ -
2025/02/18
ユニクロと競争せず“正しい”戦略ポジションを取っているアパレルとは -
2025/02/11
「あえて着ない」人が増加中 スーツ業界の復活はあるのか? -
2025/02/04
参入多いが難しいアパレルの多角化戦略、成功の秘訣は? -
2025/01/28
正しいTOC(制約理論)の理解 余剰在庫と欠品が激減する本当の理由!
この連載の一覧はこちら [61記事]
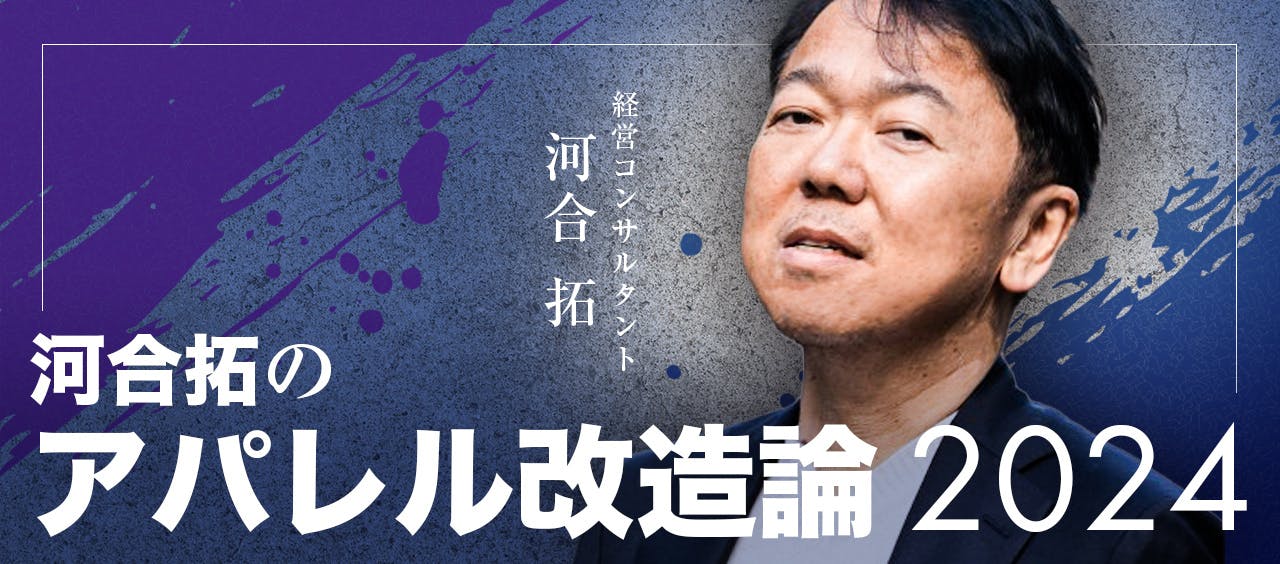
ファーストリテイリング(ユニクロ),しまむらの記事ランキング
- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ
- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは
- 2022-04-15鈴木誠社長が語る、しまむらがコロナ禍でも業績好調の理由とは
- 2025-11-04ユニクロの「棚割り」に見るインクルーシブMDへの“覚悟”
- 2021-03-05ビジネスは「一勝九敗」 ファーストリテイリングを世界的大企業に導いた“柳井哲学”
- 2022-11-29シーイン模倣騒動と大差ないアパレル業界のパクリ体質 シーインがそれでも勝つ理由
- 2025-09-30しまむら高橋新社長がめざす、 ”しまむら偏重”からの脱却の道筋
- 2021-05-11キーワードは科学、製販統合!「無敵のユニクロ」を凌駕する「知る人ぞ知る」ファッション商品
- 2023-08-28ユニクロと東レとのサステナブルな関係から生まれたリサイクルダウン
- 2023-11-14GMS衣料のジレンマと真実!イトーヨーカ堂アパレル完全撤退の必然とは
関連記事ランキング
- 2025-11-25ワコールを追い詰めた「三つの革命」
- 2025-12-02HUMAN MADE上場から考えるファッション産業の構造的限界
- 2025-11-27急拡大するリカバリーウエア市場を攻略する
- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価
- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ
- 2025-11-24間違いだらけのアパレルDX改革、根本から変えるべき「KPIの設計哲学」
- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度
- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?
- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは
- 2022-04-22ユナイテッドアローズ重松理名誉会長が語る、創業秘話とビームスを立ち上げた理由とは
関連キーワードの記事を探す
国内ユニクロ事業が売上収益1兆円を突破 ファーストリテイリング本決算を徹底分析
アパレル売上ランキング2025 ファストリの売上高3兆円台に!
百貨店を生活商圏型SCに転換!「ららテラス川口」の全貌と戦略とは?






 前の記事
前の記事

