物流はいまだ食品小売の「暗黒大陸」 経営戦略に組み込み変革する方法とは
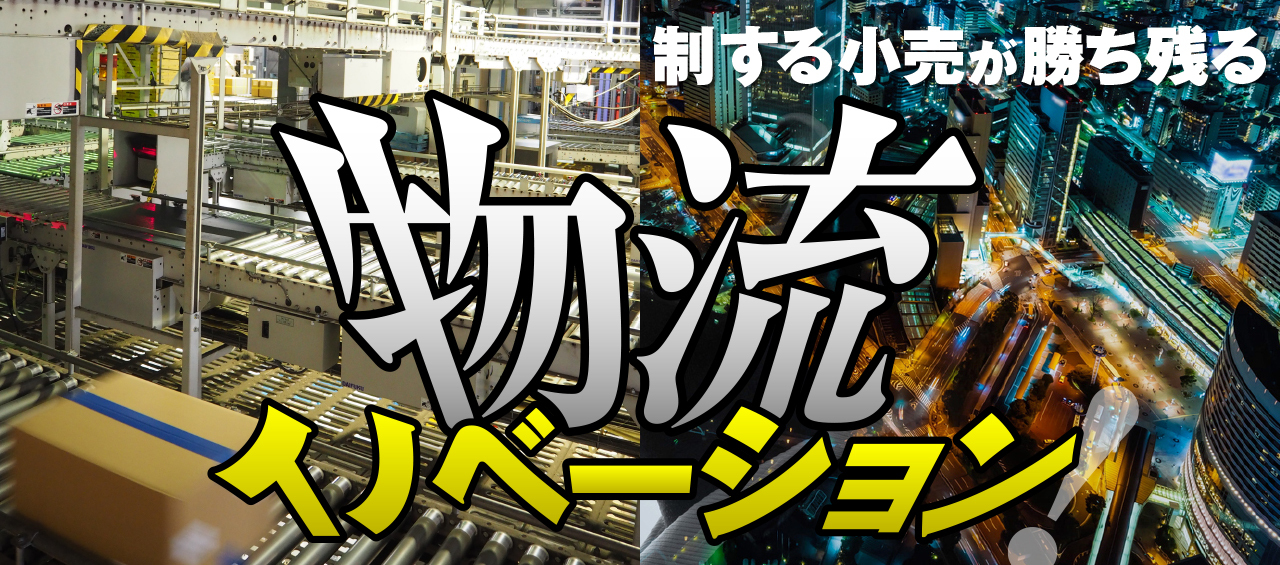
食品小売にとって物流は経営戦略の根幹
サプライチェーンの川下に位置する小売業にとって、物流は自社のビジネスを成立させるうえで欠かせないものだ。なかでも食品小売業は、食品という複数温度帯での管理を前提とした仕入れ、加工・製造、配送、品出しといった多様かつ複雑なオペレーションで成り立っている。安定した物流体制なくして、企業の成長はおろか毎日の商いすらままならない。その意味で物流は食品小売にとって、出店や商品政策と同様に経営戦略の根幹をなすものといえる。

他方で、その食品小売の物流事情は大きく変化している。1つは、人手不足の深刻化によって店舗業務の効率化が求められるなかで、プロセスセンター(PC)の活用などサプライチェーンの川上への投資が急がれること。そしてもう1つはコロナ禍でECやネットスーパーへの需要が急増し、食品小売の物流のボリュームが物理的に増えていることだ。いずれにしても、食品小売の物流のキャパシティはひっ迫しつつあり、プロセスの効率化やアップデートが求められている。
奇しくも、“コロナ特需”によって食品小売業界は軒並み業績が好調であり、ある程度の投資余力を得た企業も少なくないだろう。物流という経営戦略上の要衝をさらに強化するうえで、またとないチャンスが到来しているともとらえられる。
「戦略」に乏しかった食品小売の物流
ただ、食品小売が主体的に物流領域の革新を進めるという事例は、一部の先進的な企業を除けば、過去も今も限定的だ。消費者ニーズの多様化、業態間の競争激化、少子高齢化や人手不足の深刻化など、社会環境が目まぐるしく変化するなか、店舗フォーマットや売場づくり、商品政策の成熟度に比べると、食品小売ビジネスを支える物流の仕組み自体は、大きく変化しているとは言いづらい。
「つまるところ、『戦略』がなかった」──。食品小売の物流の取り組みについて、複数の物流コンサルタントはこう口を揃える。サプライチェーンの中で、生産者・メーカー、卸、物流、小売というそれぞれの役割が固定化し、川下にいる小売はそもそも物流領域にメスを入れるという発想に乏しかったというのだ。
これについて、ロジスティクスおよびサプライチェーン領域に知見の深いローランド・ベルガーの小野塚征志氏は、日本の小売の商慣習も影響していると指摘する。「欧米の小売市場では商品の供給を受ける側(小売業)が物流費を支払うが、日本では実質的に出荷元が物流費を持つケースが多く商品代金に物流費が最初から乗っかっているという構図。それゆえ、欧米では小売側が物流費を抑えるために物流プロセスの効率化を図ろうとする企業が多いが、日本では小売が主導して物流をテコ入れしようという動きが活発ではなかった」(同)。そのため、小売企業が物流業務に投資するといっても、設計や設備配置などは外部のベンダーやコンサルタントの知見に依存し、実際は“丸投げ”されているケースも少なくなかったという。
しかしこのままでは、自社の経営戦略や経営課題、現場(店舗)の実情や顧客の需要とリンクした物流体制は構築されず、企業としての競争力を失いかねない。そのためには小売側が主体的に、物流の領域にメスを入れることが求められる。
物流イノベーション! の新着記事
-
2021/12/15
2022年は「配達ロボット元年」 ZMPが変える、ロボットによる物流全体最適とは -
2021/12/15
ラストマイル物流で存在高まるQコマース 小売業界、ネットスーパーをどう変えるか? -
2021/12/14
食品小売の物流を激変させる「サプライウェブ」時代が到来へ!待ち受ける天国と地獄とは? -
2021/12/14
都市型MFC ニーズ拡大!米国スーパーが続々オートストアを導入する理由は -
2021/12/13
戦略物流の実践者・松浦学氏が教える、物流変革の手順と方法、課題 -
2021/12/13
国内スーパー屈指の物流体制生みの親が教える、スーパーの物流改革と投資効果測定の手法とは
この特集の一覧はこちら [12記事]
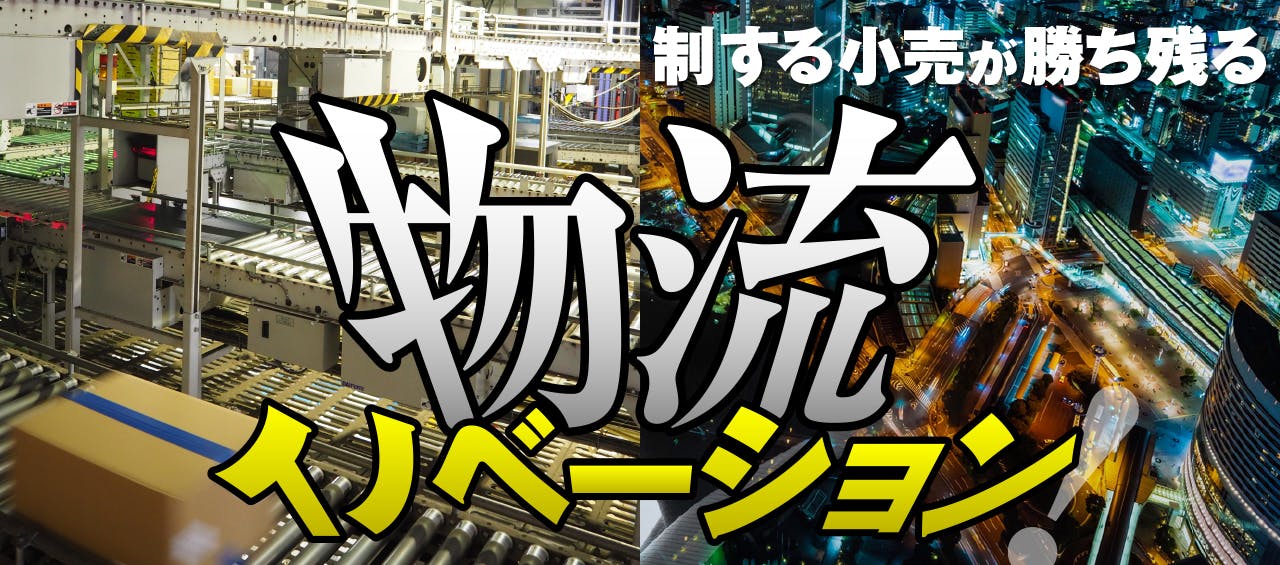
オギノの記事ランキング
関連記事ランキング
- 2025-11-19週刊スーパーマーケットニュース ブルーゾーンHDが中間決算を発表 ヤオコーは増収増益で好調
- 2025-12-04セブン-イレブンの商品配送に自動運転トラックを活用へ 実証実験を開始
- 2020-09-02モノタロウ、新物流センターに無人搬送ロボット約400台を導入
- 2023-10-06オランダ最大の小売企業「アルバート・ハイン」に今注目すべき理由
- 2024-01-11共同配送網の改善で物流危機時代を乗り切るセブン-イレブンの戦略とは
- 2019-10-28米アマゾン、商品の店頭受け取り拠点を拡大、新たにGNCなど3社と提携
- 2019-11-08国分グループが生鮮事業会社を再編、市場からの調達力を強化
- 2020-03-27プロロジス、オイシックス専用の冷蔵倉庫を着工、神奈川県で
- 2020-04-28AIとビッグデータでサプライチェーンを最適化!物流ベンチャーHacobuとライナロジクスが業務提携
- 2020-06-17ヤマト運輸、EC事業者向けの新配送サービス開始、ZOZOやヤフーが利用
関連キーワードの記事を探す
セブン-イレブンの商品配送に自動運転トラックを活用へ 実証実験を開始
アパレル企業が倉庫自動化の前に検証すべき「物流最適化の大原則」とは






