大転換期を迎えた食品スーパー業界、高すぎる労働分配率をどう引き下げるかが最重要課題に
進まぬPBによる粗利益率向上
食品スーパーにおける労働分配率が高いことは前述の通りだが、その一つの要因は分母である粗利益率が低い(一般小売業が30~40%であるのに対し、食品スーパーは25%前後が多い)ことも影響している。
粗利益率の高いPBの売上を積み上げるのが食品スーパーの至上命題なのだが、品質高いPBを一流メーカーにつくってもらうためには、一定量の発注ができる企業規模が必要であることは言うまでもない。だからこそ、食品スーパーは経営統合によって規模拡大をめざし、生き残りを図ろうとするのである。
ただ、ここにもネックがあって、日本の消費者のナショナルブランド(NB)信仰がかなり強いため、PBがなかなか浸透しないというのは各社共通の悩みだろう。イオンのPB「トップバリュ」が、食品のうちの2割程度であるらしいが、これは欧米のグローバルリテイラーが3~5割であることからすれば、決して高いとは言えない。
そのほかの食品スーパーにおいてはPBの浸透度はもっと低く、1割にも達してないというのが現状であろう。業界における合従連衡の目的は、調達基盤を拡大することにより、より品質の高いPBを開発し、PB比率を上げて粗利益率を向上させる、ということにあったといっても過言ではないだろう。
パート化推進による人件費削減が限界に達し、合従連衡によるインフラ共有とPB強化による収益改善という段階に入っていた食品スーパー業界は、コロナ禍を挟んで大きな転機を迎えることになった。コロナ禍により、巣ごもり需要という追い風を受けて、一息ついたように見えた業界は、巣ごもりが剥落するとともに減収圧力に直面せざるをえなくなった。
それだけではなく、ウクライナ戦争を契機とした世界的な需給環境の変化がこの国の経済環境を大きく変えることになった。食品とエネルギーの価格高騰、円安の進行は、長年の金融緩和政策が解決できなかったデフレ環境を一気にインフレへと転換させ、外国人労働力の来日理由を失わせ、人手不足が進行していた労働集約的産業の人件費を高騰させた。
これにより、労働分配率の高さを克服できていなかった食品スーパー業界は、中長期的な持続可能性が消失するかもしれない状況に追い込まれた。労働集約的な側面を残した日本型食品スーパーというビジネスモデル自体が曲がり角を迎えたということに他ならないのである(後半に続く)。
流通アナリスト・中井彰人の小売ニュース深読み の新着記事
-
2025/03/12
飲食店の後継者不足を支援するシェアレストラン 吉野家、新業態戦略の真意とは -
2024/09/27
丸亀製麺がはなまるうどんに大きく差をつけた「逆張り戦略」とは -
2024/07/04
コロナが明けても安心できない外食大手の経営環境と深刻な課題 -
2024/05/02
イズミが西友の九州事業を買収、激動の九州小売マーケットを制するのは? -
2024/04/03
セブン-イレブンの7NOW全国展開へ!拡大するクイックコマースへの“懸念”とは -
2024/01/17
主要駅から消える百貨店……ターミナルの新たな覇者となるのは?
この連載の一覧はこちら [20記事]
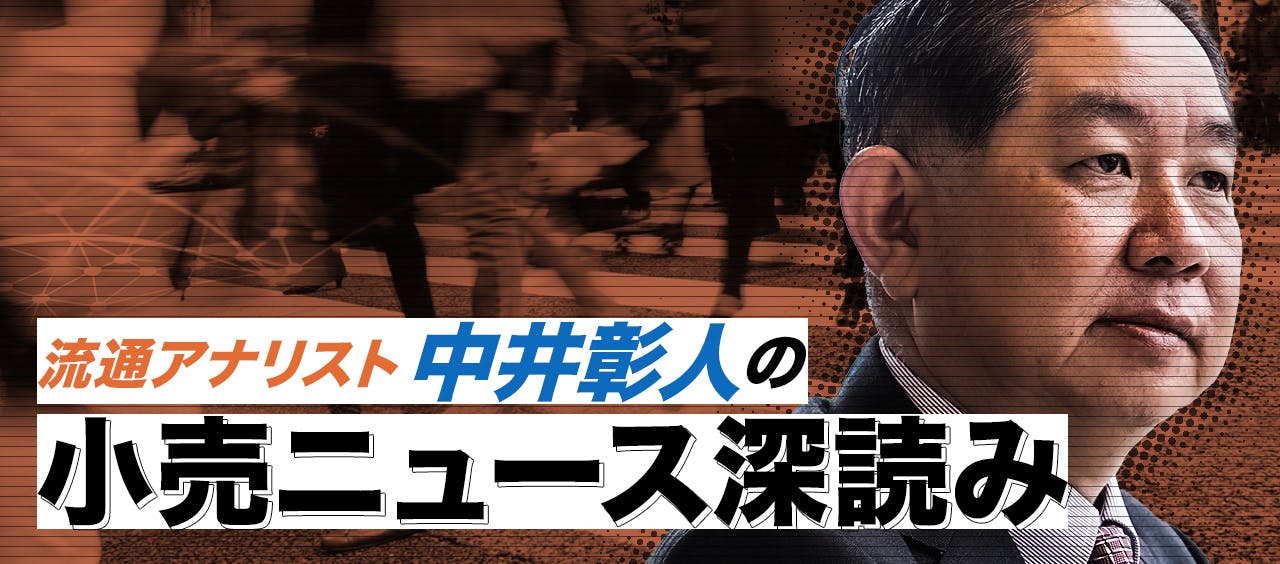







 前の記事
前の記事

