ユニクロ式多頻度・小幅値下げとシーズン末大セール、どちらが得か
今年も春夏のセールが始まっているが、ここ最近のセールは以前とは様相が変わっていることに戸惑っている消費者も少なくないだろう。値下げ率が低い、あるいはセール対象商品がかなり絞り込まれているからだ。今回はその要因について説明するとともに、ユニクロが毎週末のように商品限定で小幅の値下げセールをするやり方、普通のアパレルがシーズン末に大セールをするやり方では、企業にとってどちらが得なのか、さらにはその先にどんな価格戦略があり得るかを考えてみたい。

好調アパレルはプロパー消化率驚異の80%!
史上まれにみる円安の急進で、アパレル産業は「プロパー上代価格」(値下げをせずに商品を販売する際の正規価格)を上げざるを得なくなり、ユニクロが先陣をきって上代の価格を上げはじめ、その他のアパレルも「安易な値下げ」をやめ、昨年の秋冬を乗り越えたようだ。
おもしろい状況だったのは、これまで「値段を上げたら客が来なくなる」と信じられてきたのだが、現実にはどのアパレルも業績好調な点だ。結局、いままで身を削って値下げをしてきたのはなんだったのか、ということだ。
そもそも「上代」は、その企業がもっている「(平均)正規価格消化率」で決まる。仮に、Aという企業の「正規価格消化率」が50%だとすると、50%が正規価格で販売され、50%がディスカウントで販売されることを意味する。好調なアパレルに話を聞くと正規価格消化率が80%近辺にきているようだ。
日本全体の平均正規価格消化率が30~40%であることを考えると、80%は恐るべき数字だ。だが、これとて、いままではコストダウンをやりつくし、もうこれ以上できなくなったから「値下げを辞めた結果」であることを考えてほしい。
話を正規価格に戻すと、日本では、春夏商品は3、4月から店頭に現れ、6、7月からセールが始まり、秋冬商品は8、9月ごろから店頭に現れ、10、11月にはセールがスタートするわけだ。
これは、春夏の商品、秋冬の商品を消費者が実際に必要としている時にディスカウントするように見え、消費者にとっては「とてもお買い得」ということになるのだが、問題は、日本中のアパレルが「一斉に同じ時期にセールを行う」ことにある。また、正規販売時期(プロパー販売)といっても、「ポイントダブルキャンペーン」「クーポン」など値引きはしないものの、お買い得なプロモーションを行っているから、結局は年中実質値引きを行っているようなものだ(ポイントは販管費からコストとして落ちるので、売上にも正規価格消化率にも影響を与えない)。
河合拓氏の新刊、大好評発売中!
「知らなきゃいけないアパレルの話 ユニクロ、ZARA、シーイン新3極時代がくる!」
話題騒然のシーインの強さの秘密を解き明かす!!なぜ多くのアパレルは青色吐息でユニクロだけが盤石の世界一であり続けるのか!?誰も書かなかった不都合な真実と逆転戦略を明かす、新時代の羅針盤!
河合拓のアパレル改造論2024 の新着記事
-
2025/03/19
日本人の服がこの10年で「ペラペラ」になった本当の理由_過去反響シリーズ -
2025/03/12
ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ -
2025/02/18
ユニクロと競争せず“正しい”戦略ポジションを取っているアパレルとは -
2025/02/11
「あえて着ない」人が増加中 スーツ業界の復活はあるのか? -
2025/02/04
参入多いが難しいアパレルの多角化戦略、成功の秘訣は? -
2025/01/28
正しいTOC(制約理論)の理解 余剰在庫と欠品が激減する本当の理由!
この連載の一覧はこちら [61記事]
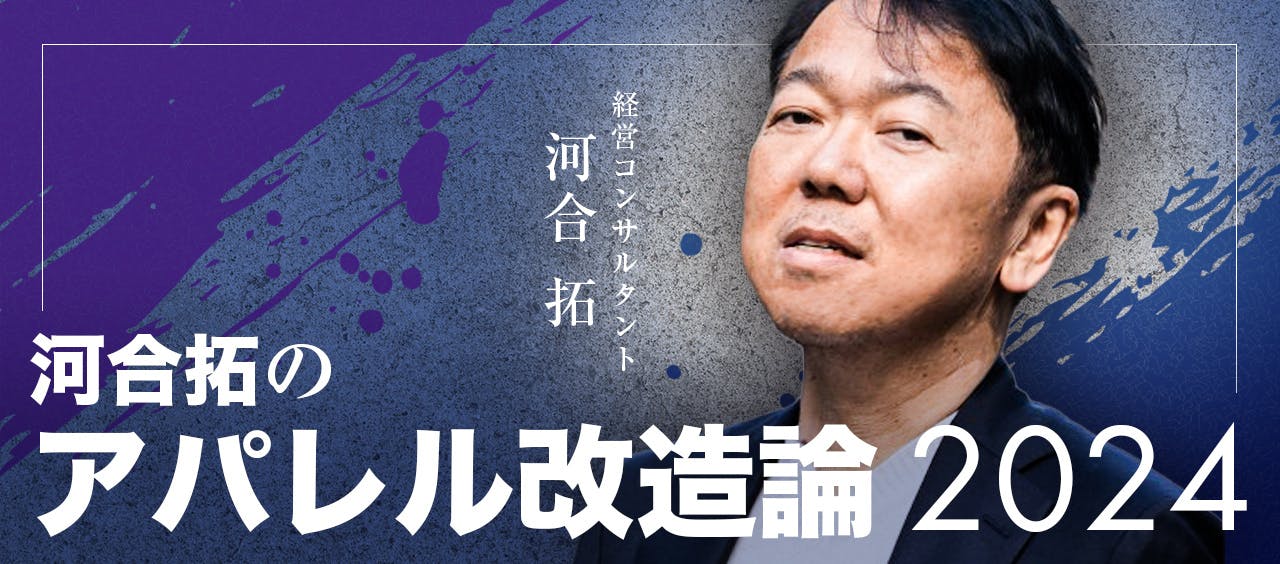
関連記事ランキング
- 2025-11-25ワコールを追い詰めた「三つの革命」
- 2025-12-02HUMAN MADE上場から考えるファッション産業の構造的限界
- 2025-11-27急拡大するリカバリーウエア市場を攻略する
- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価
- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ
- 2022-04-22ユナイテッドアローズ重松理名誉会長が語る、創業秘話とビームスを立ち上げた理由とは
- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度
- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?
- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは
- 2025-11-24間違いだらけのアパレルDX改革、根本から変えるべき「KPIの設計哲学」





 前の記事
前の記事

