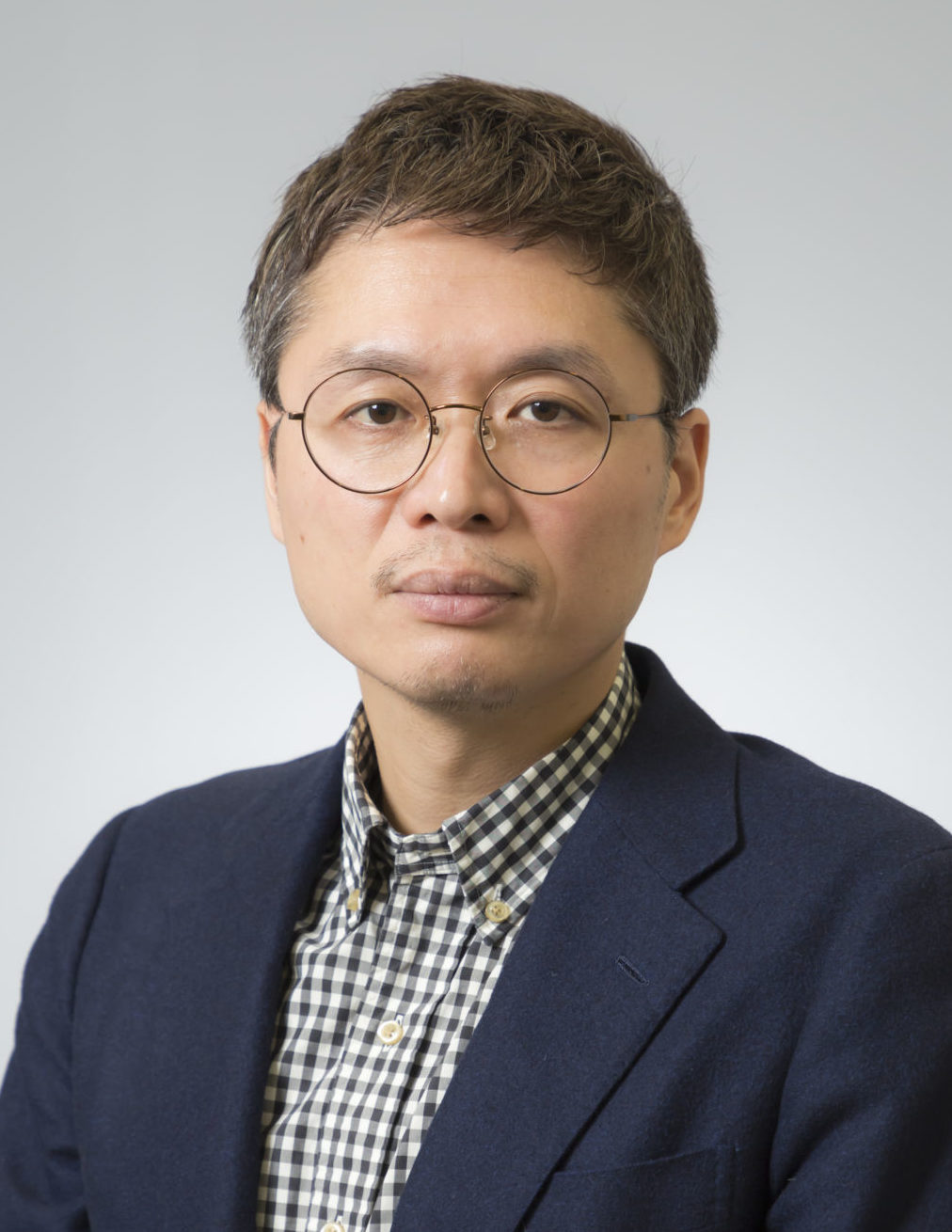「タイム・コンビニエンス」に活路 セブンイレブン永松文彦社長が「CVSの成長に限界はない」といまも断言する理由

新型コロナウイルス(コロナ)感染拡大で業績が大きく落ち込むコンビニエンスストア(CVS)業態。そうしたなかでも首位セブン-イレブン・ジャパン(東京都:以下、セブン-イレブン)は、ほかの大手CVSと比較してその減少幅を抑えることに成功している。同社はコロナ禍でどのような施策を打ち、今後のCVS市場でいかに成長を遂げようとしているのか。同社の永松文彦社長に聞いた。
店舗周辺の「生活者」の需要にフォーカス
──2020年はコロナがCVS企業の業績を直撃し、セブン-イレブンも21年2月期は減収減益となりました。しかし四半期ごとにみると、業績は回復基調にあります。

永松 CVSはこれまで、行楽や通勤といった人が移動する際に利用いただくことが多い業態でした。そのため、人の行動が制限されるコロナ禍では、セブン-イレブンでもオフィスや行楽地立地の店舗は売上が減少しました。一方で、住宅立地の店舗は“在宅需要”などの高まりで売上高が前年と比べてやや増加しました。オフィスや行楽地立地の店舗についても周辺にお住まいの方の利用は増えています。
CVSは、日常の食を中心に扱う店舗ですから、お客さまのニーズは必ず存在します。ただし、今回の感染症の流行のような環境変化によってニーズのかたちは変わります。その変化に対応し続けることが重要です。こうした考えのもとセブン-イレブンではコロナ感染拡大後、店舗周辺で生活するお客さまへの対応を強化しています。
──具体的にはどのような取り組みをしたのでしょうか。
永松 コロナ禍ではまとめ買いニーズが高まり、1人のお客さまが利用するCVSの数は減っています。ですので、そのなかで選ばれる店をつくり、また1品でも多く購入いただけるように提案力を高める必要があります。
そこでセブン-イレブンでは、店舗の売場レイアウトを「2020年度版新レイアウト」へと転換しています。具体的には、家飲み需要を取り込むべく酒類売場を拡大し、そこに総菜やおつまみの売場を連動させたレイアウトです。すでに20年度には5000店舗以上を同レイアウトに変更し、現在は対象となる約1万2000店への導入を進めている最中です。
全店一律のフォーマットから脱却し、立地や客層に応じた店づくりも進めています。店舗数が2万店を超える当社では、店によって求められる商品や品揃えが異なります。その違いに対応することで需要をより獲得できるように、店舗を
コロナが変えるビジネスモデル コンビニ作り直し! の新着記事
-
2021/05/31
コロナ禍で苦戦するコンビニ セブン‐イレブンだけ好調の意外な理由が、レシートデータ調査で明らかに -
2021/05/31
足元では郊外住宅地でも利用減の衝撃!コンビニ苦戦の理由をデータで解き明かす! -
2021/05/31
コンビニ業界苦戦のなか、セコマがコロナ禍でも既存店売上高を伸ばせた理由 -
2021/05/31
利益を加盟店と分け合い、「食の目的来店ストア」めざすミニストップの巻き返し策とは? -
2021/05/28
ファミペイ仕掛け人が語る「金融、広告で稼ぐ」コンビニの未来とは -
2021/05/28
ファミリーマート、無人決済店舗でねらうマイクロマーケットの鉱脈
この特集の一覧はこちら [17記事]

セブンイレブンの記事ランキング
- 2025-11-07週刊コンビニエンスストアニュース ローソン、クマ対策に関する基本方針を策定
- 2025-11-12週刊コンビニエンスストアニュース 「TRIAL GO」がついに東京23区に出店!
- 2025-06-26コンビニ決算2025 苦境のセブン、好調のファミリーマートとローソン
- 2025-12-02“コンビニ一本”で企業価値向上へ セブン&アイの新経営戦略の成否
- 2025-12-04セブン-イレブンの商品配送に自動運転トラックを活用へ 実証実験を開始
- 2025-10-20セブン&アイ中間決算を分析! 苦戦続く国内外のコンビニ事業回復のカギは
- 2025-11-21週刊コンビニエンスストアニュース ローソン、「盛りすぎチャレンジ」企画を実施
- 2025-10-09コンビニ市場占有率2025 市場は依然拡大も、迫られる既定路線からの脱却
- 2025-02-20週刊コンビニエンスストアニュース 米の奥深さが伝わるローソンの「日本おこめぐり」
- 2025-06-05セブン‐イレブンの真のデータ民主化生成AI基盤「AIライブラリー」とは?
関連記事ランキング
- 2025-11-07週刊コンビニエンスストアニュース ローソン、クマ対策に関する基本方針を策定
- 2025-11-10ローソンがおにぎり新戦略で掲げた「2つの軸」とは
- 2025-11-12週刊コンビニエンスストアニュース 「TRIAL GO」がついに東京23区に出店!
- 2025-06-26コンビニ決算2025 苦境のセブン、好調のファミリーマートとローソン
- 2025-12-02“コンビニ一本”で企業価値向上へ セブン&アイの新経営戦略の成否
- 2020-03-30彷徨うコンビニその7 山崎製パンがデイリーヤマザキを手放せない事情
- 2025-12-04セブン-イレブンの商品配送に自動運転トラックを活用へ 実証実験を開始
- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度
- 2025-10-20セブン&アイ中間決算を分析! 苦戦続く国内外のコンビニ事業回復のカギは
- 2025-12-04平均日販69万円! 沖縄ファミリーマート、強さの源泉は「地域密着」
関連キーワードの記事を探す
セブン-イレブンの商品配送に自動運転トラックを活用へ 実証実験を開始
2種の主食メニューを一皿で ローソン「よくばりセットメシ」新商品を発売