日本人が大好きな衣料品セール 安く買うのが難しくなる理由とは
今後、セールの値引き率が抑制される理由

さて、プロパー価格とセールのメカニズムを見てきたが、昨年よりアパレル業界で衝撃的なことが起きた。昨今の円安が原因となって、コストプッシュにより、値引き余力のあるプロパー価格をつけられなくなったのだ。日本のアパレルは99%が輸入だから、コストは為替によって大きく左右される。さすがに1ドル160円近い、近年例がない円安水準になると、上代(プロパー価格)を上げなければならない。だから、多くのアパレルが割引率を抑制したり、セール対象アイテムを減らすといった「セールの抑制」をはじめたのである。
先陣を切ってセールを抑制したのがユニクロだ。日本はユニクロがやれば他の企業も追随するので、各社一斉にセール価格を抑えにかかった。
ちなみにユニクロの場合、海外事業の売上・利益のほうがいまや大きくなったので、円安になれば海外の売上・利益・資産が大きく膨れ上がるという、いままでのアパレル企業にはなかった現象が起きている。
それ以前の日本のアパレル業界は、「輸入産業」だったので内需で利益を出していたため、「円安は苦しく、円高は儲かる」状態だった。しかし、ユニクロは円高になれば約9000億円の売上収益(23年8月期)がある日本市場が儲かることになり、円安になれば海外の売上.・利益・資産が膨れ上がる。
さて、話をセールに戻そう。多くのアパレル企業はセールを抑制したのだが、売上が落ちるどころかむしろ売上は拡大した。「セールによる買い控え」が起こらない企業がそれなりに出てきたのである。
これは、インバウンド客が、海外に店舗を持つブランドを認知し、円安効果により自国で買うよりもはるかに安く買えるため、日本でそのブランド品を買ったためである。
海外でそれなりにプレゼンスがあるアパレル企業はいまや、日本国内売上の20%程度がインバウンド売上だと言われている。
セールは今後、AIの統計処理などを使い、商品ごとに細かくダイナミックプライシングが導入されていく。セール開始時期も一斉ではなく商品ごと、また、値引率も商品ごとに変わってゆくだろう。具体的に言えば、売価変更にAIが組み込まれ、必要量から初速(最初に売られるスピード)、在庫、そして当該商品のライフサイクルなどを変数として、全体としてもっとも儲かる価格が設定されるようになる。
これによってセールでの値引き率は減ることになり、セール好きの日本人にとっては大変残念なことになる。アパレル各社の消化率はアップし、収益性も回復するわけだから、為替次第ではあるが正規価格が引き下げられる(最適化される)ことも消費者としては期待したいところだが、それは果たして、どうだろうか?
河合拓氏の新刊、大好評発売中!
「知らなきゃいけないアパレルの話 ユニクロ、ZARA、シーイン新3極時代がくる!」
話題騒然のシーインの強さの秘密を解き明かす!!なぜ多くのアパレルは青色吐息でユニクロだけが盤石の世界一であり続けるのか!?誰も書かなかった不都合な真実と逆転戦略を明かす、新時代の羅針盤!
プロフィール

株式会社FRI & Company ltd..代表 Arthur D Little Japan, Kurt Salmon US inc, Accenture stratgy, 日本IBMのパートナー等、世界企業のマネジメントを歴任。
著作:アパレル三部作「ブランドで競争する技術」「
筆者へのコンタクト
https://takukawai.com/contact/
河合拓のアパレル改造論2024 の新着記事
-
2024/12/24
「SPAだから強い」が途方もない誤解である理由と強さを決める「製販の柔軟性」とは -
2024/12/17
あなたはいくつ備える?AI時代に生き残るビジネスパーソン3つの条件とは -
2024/12/10
ワールドが三菱商事ファッション買収!進むアパレル垂直統合、2つの課題とは -
2024/12/03
ユニクロ柳井会長がウイグル綿花不使用発言に至った理由と影響、その複雑な背景とは -
2024/11/26
イタリア繊維産業に学ぶ、高くても売れるビジネスの秘密とは 染めと売り方が段違い -
2024/11/19
ユニクロ、開始から7年で明らかになった有明プロジェクトのいまとすごい成果
この連載の一覧はこちら [52記事]
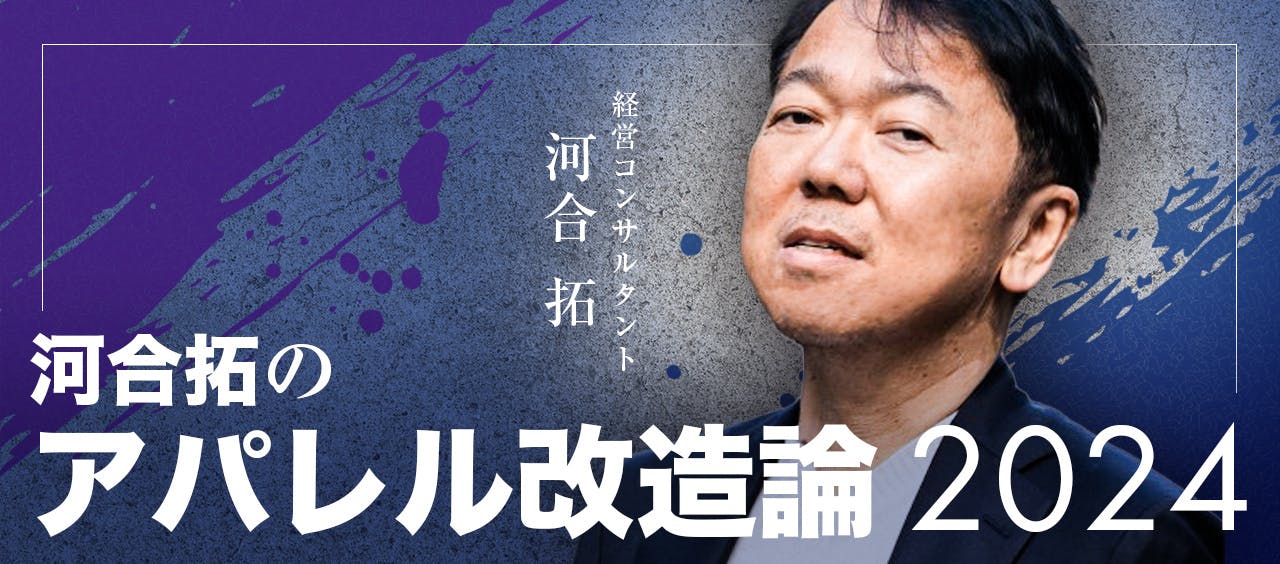
関連記事ランキング
- 2024-12-10ワールドが三菱商事ファッション買収!進むアパレル垂直統合、2つの課題とは
- 2024-12-03ユニクロ柳井会長がウイグル綿花不使用発言に至った理由と影響、その複雑な背景とは
- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?
- 2024-12-17あなたはいくつ備える?AI時代に生き残るビジネスパーソン3つの条件とは
- 2024-12-24「SPAだから強い」が途方もない誤解である理由と強さを決める「製販の柔軟性」とは
- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価
- 2023-08-08EC時代にスクロールとベルーナだけ好調 生き残るカタログ通販、死ぬカタログ通販
- 2023-09-26無印良品の一部となる三菱商事ファッションとユニクロ:Cの成功が意味することとは
- 2024-11-26イタリア繊維産業に学ぶ、高くても売れるビジネスの秘密とは 染めと売り方が段違い
- 2024-01-02勝ち組はSPAではなく「無在庫型」へ 2024年のアパレル、5つの受け入れ難い真実とは





 前の記事
前の記事





