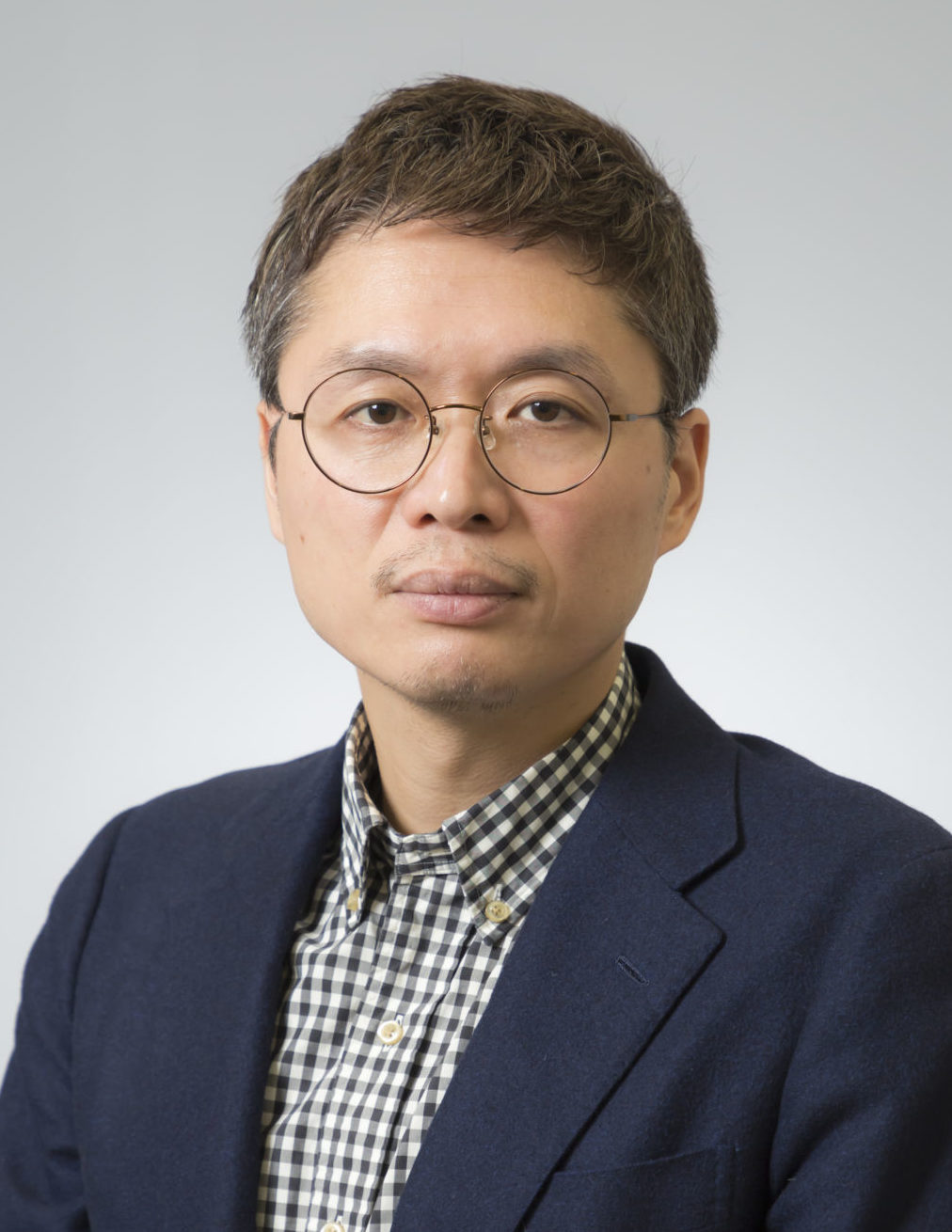WORKMAN Plus(ワークマンプラス)が急増殖!一般消費者開拓に成功した2つの理由とは!?

作業服専門のフランチャイズチェーンを展開するワークマン(群馬県/小濱英之社長)は一般消費者にターゲットを拡大したWORKMAN Plus(ワークマンプラス)の出店を昨年9月よりスタート。作業服ならではの機能性と低価格が一般消費者から高い支持を受けている。今後の出店はすべてこのワークマンプラス業態。売場づくりの特徴とヒットの背景を解説する。
なぜ、一般消費者開拓に成功?その要因は2つある
ららぽーと立川立飛3Fの突き当り、目的来店性の高くないアパレル店としては決して一等立地とは言えない場所に、その行列店はある。平日朝の早い時間帯であればゆったり買い物できるが土日曜ともなると瞬く間に長蛇の列が出来上がる。ここは昨年9月にオープンしたワークマンプラスの1号店、ららぽーと立川立飛店だ。わずか60坪の売場面積で、当初予定の2.5倍の3億円を売り上げるペースで推移する。
作業服専門チェーンのワークマンはなぜ競争の激しい一般消費者マーケットに進出したのか、そしてなぜ高い支持を得ることができたのか?

1つ目は作業服に対するニーズの変化がある。近年若い職人を中心に、作業服に対してカジュアル服のようなデザイン性が求められるようになった。電車通勤の職人も増えるなど、街を歩いても違和感のない恰好が求められ、次第にオンオフ兼用といった着用シーンの拡大へと発展していった。そのため迷彩柄の作業用ブルゾンにアディダスなどスポーツメーカー製の作業靴を合わせるといった動きが職人の間で次第に浸透していったのだ。
一方ワークマンは2015年ごろからプライベートブランド(PB)商品の開発に力をいれるようになり、SPA(製造小売)化に舵を切るようになる。すっきりしたデザインでカラーバリエーションを拡充させた作業服から始まり、作業服の持つ機能性を活かして、一般消費者がスポーツやアウトドアシーンで着用できるレインウェアやスポーツウェアなどの自社ブランドを次々に展開し、そのラインナップを広げていった。

つまり、作業服のカジュアル化と、作業服起点で機能性を打ち出したワークマンのPB開発という2つの動きが重なり、一般消費者にも受け入れられる素地が整ったというわけだ。
それを受けワークマンは、「高機能で低価格というサプライズ」という価値を消費者に広く知ってもらうアンテナストアの役割を果たす店舗を開発すべく、ららぽーと立川立飛店を開設。メディアがこぞって取り上げたこともあり、同社の想定をはるかに上回る売上を記録し、その後の出店に弾みがついたという経緯だ。
2号店で完成したハイブリットストアモデル!

1号店では、500点あるPBのうち300点を品揃えする。このことからわかるとおり、既存ワークマン店舗でも扱っている商品だけを取り扱う。ビジュアル・マーチャンダイジングを導入し、一般消費者向けの色使いの商品を目立たせることで、新業態を作り上げた。ショッピングセンター(SC)内店舗ということで、従来とはオペレーションが異なるため、販売や品出し業務について、外部に委託する方式で運営している。
1号店の成功を受け、多店舗出店の可能性を探った2号店が、ロードサイド型の川崎中野島店である。最寄り駅からは徒歩約14分と離れており、車や自転車での来店がメーンとなる。売場面積は90坪で、既存ワークマン業態の標準規模に当たる。店内入口側の左半分が一般向けの売場づくりで、右半分が作業用品や作業靴も含めた職人向けの売場というハイブリット型になっている。売場の境目にはスタイリッシュなワークウェアを配置して、違和感なく売場を繋ぐ。また壁面上部に各商品の使用シーンなどを表すパネルを設置し、何がどこにあるか視認しやすい工夫も行う。職人の客数はそのままに、一般消費者の客数が増えたことで、同規模の既存店と比べ、売上はほぼ倍増している。
同社では既存ワークマン店舗の平均年商が1億334万円だが、路面店のワークマンプラスは2億円、SC内のワークマンプラスは3億円を目標にしている。今後の出店はすべてワークマンプラス。既存店の業態転換も進めながら、19年9月までにワークマンプラスを35店舗体制とする計画だ。

19年3月に入ってからは、3月14日に新店の練馬下石神井店など4店舗をオープン(うち1店舗はワークマンからの業態転換)しており、翌週の21日にも同じく4店舗を出店(うち2店舗はワークマンからの業態転換)する計画だ。