飲食店の後継者不足を支援するシェアレストラン 吉野家、新業態戦略の真意とは
吉野家ホールディングス(東京都:以下、吉野家HD)は2024年10月に飲食店の事業承継を支援する新事業「アトツギレストラン」を開始した。後継者不足に悩む飲食店と開業希望者をマッチングし、店舗の継続を支援する仕組みだ。しかし、この取り組みには、単なる業界支援を超えたねらいがあるのではないか。外食業界における新業態の開発が難しくなるなか、吉野家がこの事業を始めた背景を探る。

真のねらいは「買収候補育成」か
吉野家HDが飲食店の事業承継を支援するサービス 「アトツギレストラン」 を開始した。
後継者不足に悩む飲食店経営者と、開業をめざす人をマッチングし、店舗の継続を支援する仕組みである。このサービスを24年10月に開始したのは、吉野家HDの100%子会社であるシェアレストラン(東京都)だ。同社はこれまで飲食店のアイドリングタイムを活用し、開業希望者に店舗を貸し出すサービスを手がけてきた。
このシェアレストラン事業は、吉野家HDの「3ヶ年グループ中期経営計画(2022年度~2024年度)」において、「顧客の多様なニーズに応え、新たなブランドを育成する」ことを目的とした事業と位置づけられている。
シェアレストラン事業の趣旨は、アトツギレストランのプレリリースによれば以下の通りだ。飲食店は新規開業件数が多い一方で廃業率が高い。そのため、従来のように先行投資をしてから集客する「ハイリスク・ローリターン」なモデルではなく、まずは店舗を間借りしてファンを作り、成功の見込みが立った段階で本格的に投資する「ローリスク・ハイリターン」な仕組みを構築するとしている。つまり、開業リスクを低減することで、開業者を増やしていこうという取り組みなのだ。
アトツギレストランもこの「シェアレストラン」と同様の考えに基づいており、事業承継が必要な飲食店を引き継ぐことで、開業者がローリスクで新たに事業を始められるよう支援する。これは業界の活性化に貢献する意義のある取り組みだ。しかし、ここで気になるのは 吉野家HDにとってのメリットだ。この事業を展開する同社にはどのようなねらいがあるのだろうか。
アトツギレストランのプレスリリースの末尾部分に、吉野家HDがこの事業を展開する目的が簡潔に記されている。それによれば、同社は「事業継承希望者と飲食店の双方の環境改善支援をすることで、新しい開業モデルの創出を図り、外食産業の更なる発展の一助となることを企図」している。
この方針を見ると、吉野家HDは単なる業界支援にとどまらず、開業希望者を初期段階から支援し、将来的に成功しそうな外食ベンチャーを早期に発掘することで、M&A(合併・買収)の候補として育成していくという戦略を持っていることがわかる。「シーズ(種)」の段階、あるいは「苗」の段階から有望な企業を囲い込むことで、効率的に成長させるという考え方だ。
一見すると、このようなM&Aの方法は遠回りで非効率に思えるかもしれない。しかし、外食産業は「水商売」とも言われるように、流行の予測が難しい業界である。なおかつ、 大ヒットした企業は株価が高騰しているため、投資効率が悪い。
だからこそ、有望な外食ベンチャーが小規模なうちに支援し、将来の成長を見据えて関係を築いておくという戦略を吉野家HDは採ったわけだ。
流通アナリスト・中井彰人の小売ニュース深読み の新着記事
-
2025/11/27
PPIHが「食品強化型ドンキ」を始動!スーパー業界に迫る“第3の黒船”となるか -
2025/08/29
群雄割拠がついに終焉? 決算ランキングから読み解く食品スーパーの現在地 -
2025/06/12
上場食品スーパーの2024年度決算 物価高がもたらした「増収減益」の実態とは -
2025/04/29
西友買収のトライアル、そのビジネスモデルの強さを小売ウォッチャーが解説! -
2025/03/12
飲食店の後継者不足を支援するシェアレストラン 吉野家、新業態戦略の真意とは -
2024/09/27
丸亀製麺がはなまるうどんに大きく差をつけた「逆張り戦略」とは
この連載の一覧はこちら [24記事]
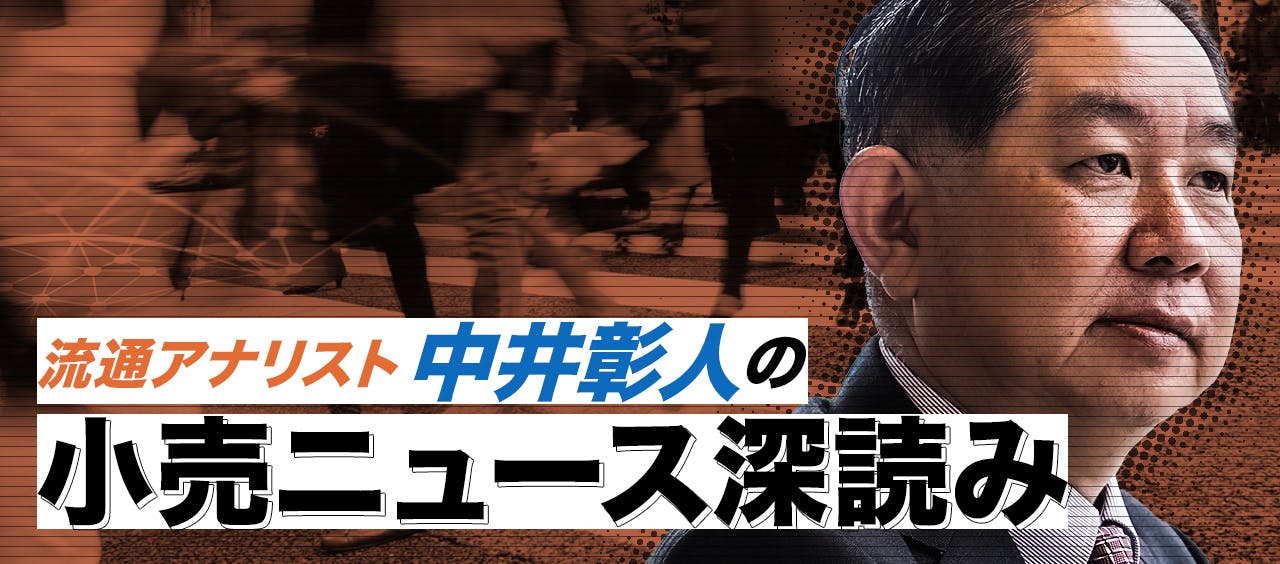
吉野家の記事ランキング
- 2025-03-12飲食店の後継者不足を支援するシェアレストラン 吉野家、新業態戦略の真意とは
- 2024-09-27丸亀製麺がはなまるうどんに大きく差をつけた「逆張り戦略」とは
関連記事ランキング
- 2025-11-05ワタミの宅食が新商品を発売 高齢者に寄り添う「一食450円」の挑戦
- 2022-12-19プレナスが創業家によるTOBで上場廃止へ! 今後の上場オーナー企業の在り方を考察
- 2025-11-18ワタミ、26年3月期中間決算を発表 通期で増収増益の着地を見込む
- 2021-10-18焼肉のファストフード化戦略とは?一人焼肉推奨店「焼肉ライク」躍進の秘訣を有村壮央社長に聞く
- 2023-08-03ロイヤルホストがコロナ前よりも売上水準が上がっている複数の理由とは
- 2022-12-142席の予約確保に40万円?飲食業界震撼の新サービス「食オク」とは
- 2023-02-28ゼンショーがロッテリアを買収へ! 買収側と売却側、それぞれの思惑は
- 2023-04-07好調の「バーガーキング」社長インタビュー 28年末までに店舗数を3倍弱に増やす計画を語る
- 2020-10-02サイゼリヤでアルバイトした星付きシェフが心底驚いた徹底「カイゼン」の凄み
- 2024-07-04コロナが明けても安心できない外食大手の経営環境と深刻な課題






 前の記事
前の記事



 クローガーが予測「25年の5大フードトレンド」、セインズベリーのアルディ対策とは
クローガーが予測「25年の5大フードトレンド」、セインズベリーのアルディ対策とは