「SPAだから強い」が途方もない誤解である理由と強さを決める「製販の柔軟性」とは
今回はSPAについてあらためて考えてみたい。「SPAだから強い」と説明する人は何人もいるが、では、なぜSPAだと強いのか、そのメカニズムをキチンと説明できた人を私は見たことがない。結局、「自社工場をもっているからSPAだ」→「SPAだから競争勝ちする」という極めて単純なロジックで考える人が多く、この理屈のまま買収を決めてしまうファンドや企業が後を絶たない。また、今後の成長戦略をたてるうえでSPAを前提とした計画をたて、理由もなく製造設備を持ってしまうアパレルも枚挙にいとまがない。
でも、よく考えていただきたい。服を買うのは一般消費者で、彼ら、彼女らにとって新しい価値が生まれない改革は、何をやっても何も変わらない。ここに、私はSPAを再検証する意味を見いだすのである。ということで今回は、改めてSPAとは何かに迫ってみたいと思う。

製造と販売を併せ持つ=強い とはならない理由
SPAは「製造小売業」と一般に翻訳され、製造と小売、言い換えれば「生産」と「販売」を一つの会社が機能として持っていればSPAだと解釈されている。
しかし、本連載で何度も指摘してきたように、SPAの元々の英語は“Speciality store retailer of Private label Apparel”で「自主ブランドを持つアパレル専門店」が正しい意味である。自主ブランドを持つアパレル専門店はめずらしくはなく、それ自体がとりわけ競争優位性を持つものではないのである。
だから「SPAが製造小売業である」「SPAだから強い」という解釈がいかに誤訳で無意味であることはおわかりになるだろう。それでも「SPA神話」は消えるどころか、私達の意識の深い底に沈殿しすでに「常識」として定着しており、私は非常に危険だと思っている。
すでにSPAの定義論は過去幾度もしたので、モデルとしてのSPA、とSPAのメカニズムについて論じてみたい。SPAとは「製品のレシピをアパレルが持っている」「自分の店で自由に売れる」ということが特徴だ。製造機能と販売機能があることではない。
例えば、自社工場をもっていても、他のアパレル向けにも製品をつくっているイタリアのファクトリーメーカーのようなブランドはSPAではない。また、製造機能をもっておらず、百貨店に納めているような形態は「疑似SPA」と自らいうアパレルもいるが、販売員まで自社社員ではないため、「自由に」陳列することもできず、これもSPAとはいえない。
ではモデルとしてのSPAの本質は何だろうか?
河合拓氏の新刊、大好評発売中!
「知らなきゃいけないアパレルの話 ユニクロ、ZARA、シーイン新3極時代がくる!」
話題騒然のシーインの強さの秘密を解き明かす!!なぜ多くのアパレルは青色吐息でユニクロだけが盤石の世界一であり続けるのか!?誰も書かなかった不都合な真実と逆転戦略を明かす、新時代の羅針盤!
河合拓のアパレル改造論2024 の新着記事
-
2025/03/19
日本人の服がこの10年で「ペラペラ」になった本当の理由_過去反響シリーズ -
2025/03/12
ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ -
2025/02/18
ユニクロと競争せず“正しい”戦略ポジションを取っているアパレルとは -
2025/02/11
「あえて着ない」人が増加中 スーツ業界の復活はあるのか? -
2025/02/04
参入多いが難しいアパレルの多角化戦略、成功の秘訣は? -
2025/01/28
正しいTOC(制約理論)の理解 余剰在庫と欠品が激減する本当の理由!
この連載の一覧はこちら [61記事]
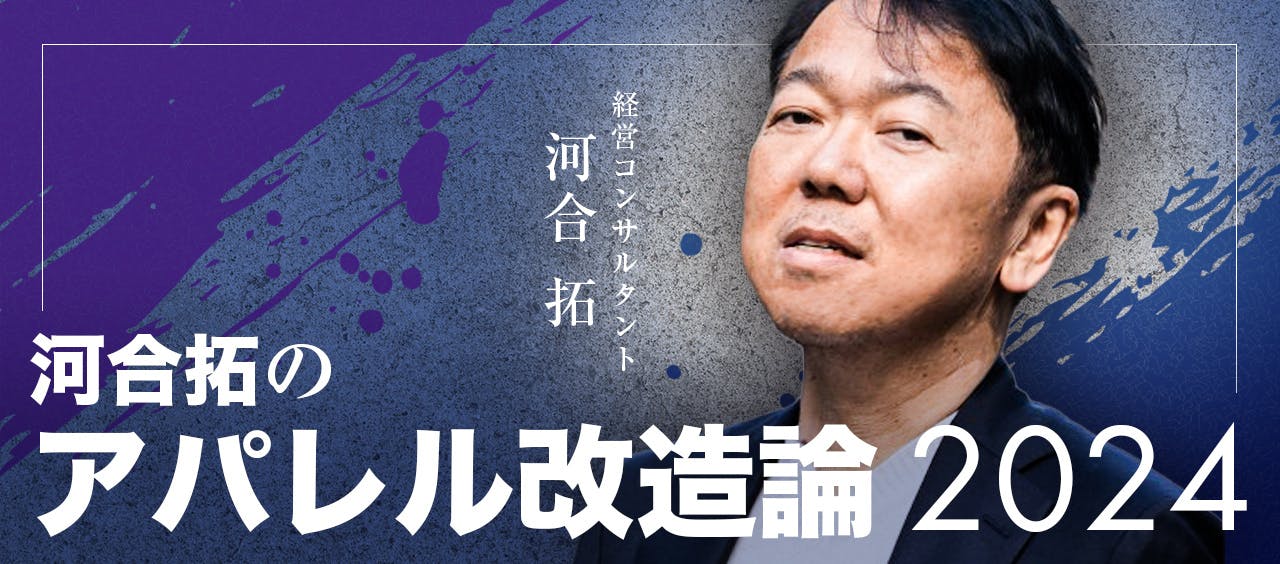
関連記事ランキング
- 2025-11-25ワコールを追い詰めた「三つの革命」
- 2025-12-02HUMAN MADE上場から考えるファッション産業の構造的限界
- 2025-11-27急拡大するリカバリーウエア市場を攻略する
- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価
- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ
- 2022-04-22ユナイテッドアローズ重松理名誉会長が語る、創業秘話とビームスを立ち上げた理由とは
- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?
- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは
- 2025-11-24間違いだらけのアパレルDX改革、根本から変えるべき「KPIの設計哲学」
- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度





 前の記事
前の記事

