ユニクロがZOZOに出店しない当然の理由と今後のECモールとの付き合い方
私は前回、日本企業の夢展望が巨大ECモールを世界中で展開する「Temu」に出店する疑問と懸念点を指摘した。今日は、こうしたECモールに対してアパレルはどう対応すべきか、今後のECモールとの付き合い方について持論を展開したいと思う。

ECモールは「顧客のバケツ」を保有するプラットフォーマー
まずはオンラインモールのビジネスモデルについて考える。モールとは、いわば、「顧客のバケツ」のようなものだ。そのバケツには服を買ってくれる顧客が山のようにいて、そのバケツの中で「顧客の奪い合い」を同じモールに出店している競合アパレルと行うのである。
モールにしてみれば、誰が勝とうが関係がない。結果的に、例えば1億円の売買がそのモールを通じてあがれば、それに応じた「通行料金」を頂けるからだ。つまり、モールというのは、テナントであるアパレル企業から見れば、高度にルール化された「プレイグランド」であるということである。そして、誰かが勝とうが、負けようが関係ない。取引高が大きければ、通行料金を沢山もらえるし、小さければもらえない。それだけである。
集客力の高いオンラインモールは、きわめて強い存在だ。例えば、○○セール!などといって、クーポンや期間限定セールを頻繁に行っているわけだが、そのセールのディスカウント料金をテナントに負担してもらう(テナントがモールのセールを手伝って、値引きをする)ことで、モールの自社リスクを極力減らしている。
くどいようだが、モールの収益源は「通行量の総和(から発生する手数料と広告料)」だから、それがセールから来ようが、プロパーから来ようが関係ない。
極端な例として、「オール70%ディスカウントセール!」というキャンペーンを行ったときのことを考えてみよう。
アパレルテナントは大赤字になるが、モールは「ディスカウントなりの通行量に応じた手数料」を頂くことができ、施策によって売上が最大化されるので、むしろディスカウントは歓迎すべき打ち手なのだ(実際は、アパレルテナントの通行量に応じた手数料には細かな計算式があって、それほど簡単ではないのだが、ここはあえて分かりやすく書いておく)。
河合拓氏の新刊、大好評発売中!
「知らなきゃいけないアパレルの話 ユニクロ、ZARA、シーイン新3極時代がくる!」
話題騒然のシーインの強さの秘密を解き明かす!!なぜ多くのアパレルは青色吐息でユニクロだけが盤石の世界一であり続けるのか!?誰も書かなかった不都合な真実と逆転戦略を明かす、新時代の羅針盤!
河合拓のアパレル改造論2024 の新着記事
-
2025/03/19
日本人の服がこの10年で「ペラペラ」になった本当の理由_過去反響シリーズ -
2025/03/12
ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ -
2025/02/18
ユニクロと競争せず“正しい”戦略ポジションを取っているアパレルとは -
2025/02/11
「あえて着ない」人が増加中 スーツ業界の復活はあるのか? -
2025/02/04
参入多いが難しいアパレルの多角化戦略、成功の秘訣は? -
2025/01/28
正しいTOC(制約理論)の理解 余剰在庫と欠品が激減する本当の理由!
この連載の一覧はこちら [61記事]
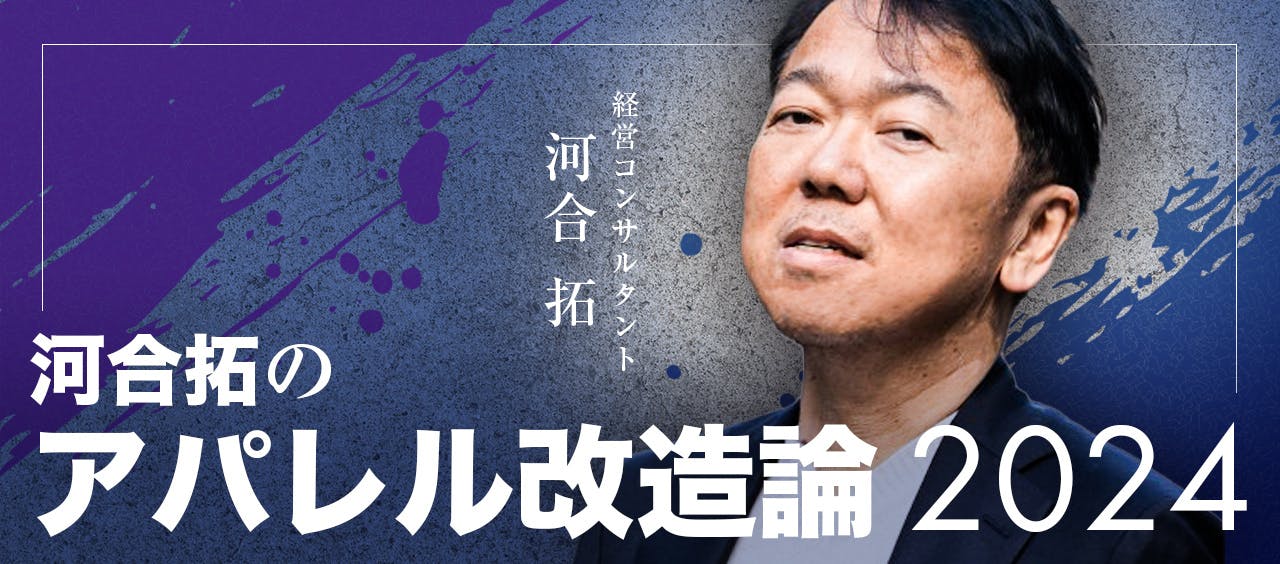
関連記事ランキング
- 2025-11-25ワコールを追い詰めた「三つの革命」
- 2025-12-02HUMAN MADE上場から考えるファッション産業の構造的限界
- 2025-11-27急拡大するリカバリーウエア市場を攻略する
- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価
- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ
- 2022-04-22ユナイテッドアローズ重松理名誉会長が語る、創業秘話とビームスを立ち上げた理由とは
- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度
- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?
- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは
- 2025-11-24間違いだらけのアパレルDX改革、根本から変えるべき「KPIの設計哲学」





 前の記事
前の記事

