「時代遅れ」を感じた小売業が実践すべき「出島戦略」とは?
利益のためのPB戦略は失敗する自明と成功のためにユニクロが行った新提案とは
「『顧客起点』という言葉はもう古くなっています。新しいコンセプトはありませんか」という質問を、ある経営者から受けた。しかし、この質問こそ、そのアパレルがダメになった体質を現わしている
小売事業でPB化が盛んだ。その実態は「売れている商品を自分で作れば粗利率が向上するだろう」というレベルだ。本来であれば、顧客にとって既存のブランドが提供できないが、自らリスクをとってでもやりたいことがあるからPBを作るべきなのだ。結果的に、ナショナルブランドの「模倣商品」がタケノコのように生まれる。当然、内部収益性を高めるためのPBなど消費者にとってなんの価値もない。これが小売事業のPBがうまくいかない理由だ。
ユニクロが1990年代後半から快進撃を遂げたのは、商社を中抜きし、中国の工場と直接取引を始めたからだという総括が一般的だがそれは本質ではない。ユニクロ以前のアパレルは、「安かろう、悪かろう」「高かろう、良かろう」という二軸でマーケティングを行ってきた。
ここに、「安かろう、良かろう」という新たな価値軸を市場に供給することで、「服なんてこんなもんだ(安くても良いものは当たり前なんだ!)」という意識を消費者に提案しプレーンな衣料品をファッションスタンダードに組み込んだのだ。つまり、自ら新しいファッションの世界観を作り上げ、それを支える物流システムをグローバル手作り上げたわけだ。ユニクロの成功は、「売れているものをちょっと安くしよう」という、模倣戦略から生まれたものではない。
いまどき展示会発注などやっていても、自らのリスクで素材を押さえ、商品をどんどん補充するアパレルに勝てるはずなどない。「最近では当社も先行発注型に変えています」などという話も聞くが、変えたのは発注形態だけで、素材一つ押さえられない体質、結果的に追加発注さえできない状況は昔のままというケースがほとんどだ。リスクをとるのはよいが、リスクを「コントロール」することができていないのである。
なんの施策もないまま、展示会発注をやめてもリスクは増えるだけで、商品は何も変わらない。この事例も、リスクとリターンの見合いだけで「儲かりそうだ」というだけでものごとを進めてゆき、「顧客にとって何を提供するのか」という本質的な議論がないまま見切り発車されるという点では同じである。
マービン・バウアーの著書「経営の本質」に、経営の目標は利益を上げることではなく、製品やサービスを提供することで、利益を上げる「資格を得ること」だ、と書かれている。企業は事業活動を通し、社会に対して価値を提供し、その「結果」として利益がついてくるという事業の本質について述べられている。自らのブランドは、顧客にとって何を提供しているのか、また、それは他社と比べて何が違うのかという議論を徹底して行うべきだろう。そこから、自社しか提供し得ないブランドの顔を持つべきなのだ。
 河合拓氏の新刊、大好評発売中!
河合拓氏の新刊、大好評発売中!
「知らなきゃいけないアパレルの話 ユニクロ、ZARA、シーイン新3極時代がくる!」
話題騒然のシーインの強さの秘密を解き明かす!!なぜ多くのアパレルは青色吐息でユニクロだけが盤石の世界一であり続けるのか!?誰も書かなかった不都合な真実と逆転戦略を明かす、新時代の羅針盤!
プロフィール

株式会社FRI & Company ltd..代表 Arthur D Little Japan, Kurt Salmon US inc, Accenture stratgy, 日本IBMのパートナー等、世界企業のマネジメントを歴任。
著作:アパレル三部作「ブランドで競争する技術」「
筆者へのコンタクト
https://takukawai.com/contact/
河合拓のアパレル改造論2024 の新着記事
-
2025/03/19
日本人の服がこの10年で「ペラペラ」になった本当の理由_過去反響シリーズ -
2025/03/12
ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ -
2025/02/18
ユニクロと競争せず“正しい”戦略ポジションを取っているアパレルとは -
2025/02/11
「あえて着ない」人が増加中 スーツ業界の復活はあるのか? -
2025/02/04
参入多いが難しいアパレルの多角化戦略、成功の秘訣は? -
2025/01/28
正しいTOC(制約理論)の理解 余剰在庫と欠品が激減する本当の理由!
この連載の一覧はこちら [61記事]
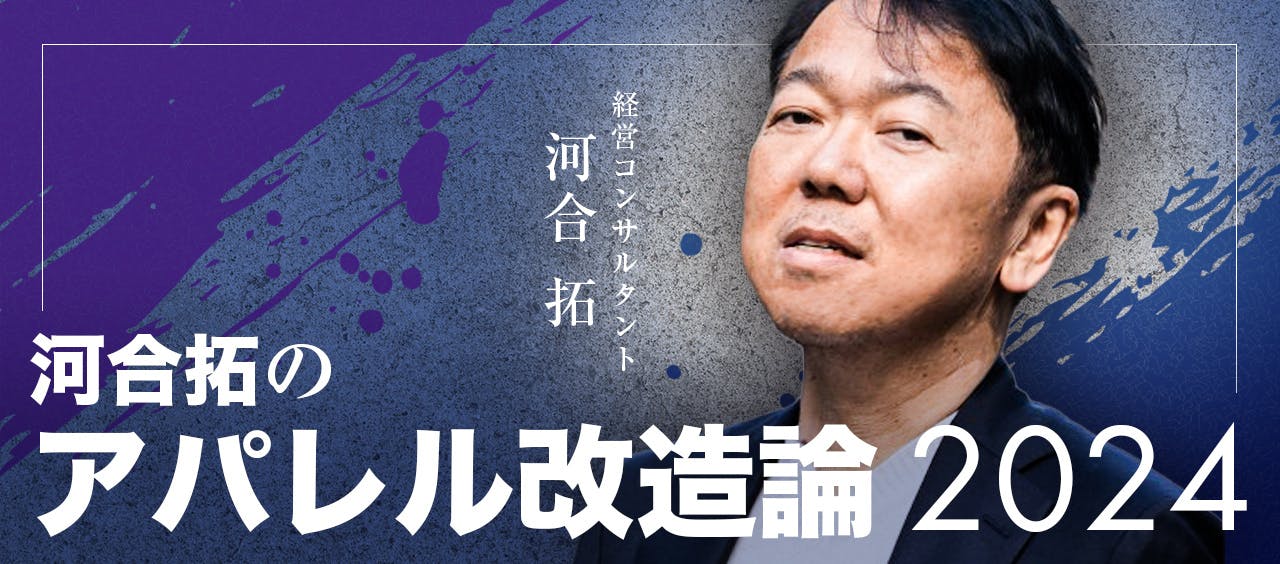
関連記事ランキング
- 2025-11-25ワコールを追い詰めた「三つの革命」
- 2025-12-02HUMAN MADE上場から考えるファッション産業の構造的限界
- 2025-11-27急拡大するリカバリーウエア市場を攻略する
- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ
- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価
- 2025-11-24間違いだらけのアパレルDX改革、根本から変えるべき「KPIの設計哲学」
- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度
- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?
- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは
- 2022-04-22ユナイテッドアローズ重松理名誉会長が語る、創業秘話とビームスを立ち上げた理由とは





 前の記事
前の記事

