違いは「顧客サイド」にあり オムニチャネルとOMOの本質的な違いとは何か?
本日は、アパレル業界のチャネル戦略の変遷についてまとめたうえで、最新の戦略的なOMO(オンラインとオフラインの融合)について解説したい。

ECで服が売れる理由はリアル店舗の存在にある
アパレル業界のチャネル戦略の変遷をおさらいしよう。
2000年、ECが大きく拡大すると、「ECでは服は売れない。さわれないからだ」という議論と「いや、ECでも十分服は売れる」という2の陣営がでてきた。今この答えはすでに出ている。「ECでも服は十分売れる」、だ。
生地の手触りや肌触り、材質感を表す「風合い」という言葉がある。これをアパレル業界人は重要視しているのだが、服を指でつまんで揉むように「風合い」を確認するのは服作りのプロか繊維産業に勤めている人だけ。実は、一般消費者は「風合い」をそれほど気にしない。
また、町に出れば服を売っている店は山のようにあり、そこで色々なデザインの服を試着しているため、自分に合う服、合わない服などすでに分かっているということもある。
だから、世の中が完全にECだけだと服は売れない可能性は高いが、日本のアパレル消費の80%はリアル店舗なので、消費者は似よりの服や実際の服を近所や繁華街の店舗などで試着することができる。
マルチチャネルとO2O
こうして、衣料品のEC販売は売れ、成長していった。当時は、「毎年ZOZO(と同様の会社)が一社ずつできる」と言われたほどECビジネスは色めきだっていた。企業側もこの成長を取り込むためECを立ち上げるのだが、当時のECはパソコンが中心だったため、「リアル店舗は外出先でオンタイムに」「ECは自宅で夜間や通勤時間に」という具合に使い分けることが一般的だと考えられていた。
こうして、できあがったのが「マルチ・チャネル」(オンラインとオフラインのミックス)である。
こうして、否が応でもECについて学ぶ必要がでてきた日本のアパレルは、EC独特の経営管理手法に四苦八苦しながらもECを立ち上げていった。しかし、この時点からすでに「先が見えている企業」と「昔の手法から脱却できない企業」にわかれていったのである。「昔の手法しか見えない企業」は、ECを一つの店舗と位置づけ、館(やかた)を持つかのごとく、サーバーを借りて初期投資を少なくし費用を変動費化したのである。
当時私は、世界のリテール業界のトップファームであるカートサーモンに在籍しており、米国にアマゾンの戦略、EC全般にわたる戦略を聞いたものだった。
当時カタログ通販の社外役員をしていたこともあり、CPA(顧客獲得コスト)、CPO(コンバージョン獲得コスト)、LTV(顧客生涯価値)という考え方を熟知しており、盛んに産業界に「モールにはでるな、客をとられるぞ」と発破をかけたのだが、その叫びは完全に無視された。
話をチャネル戦略にもどすと、このように初期投資に後れを取ったアパレル企業は、ネットガリバーと呼ばれるアマゾン、楽天、ZOZOに対抗するため、彼らが資産としてもっていないリアル店舗を利用し、リアル店舗に来た個客をECへ誘導しCPAを極小化しようと考えたのである。これが、O2Oだ(オンライン・トゥー・オフライン:オンラインからオフラインへ個客を送迎する)。
河合拓のアパレル改造論2024 の新着記事
-
2025/03/19
日本人の服がこの10年で「ペラペラ」になった本当の理由_過去反響シリーズ -
2025/03/12
ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ -
2025/02/18
ユニクロと競争せず“正しい”戦略ポジションを取っているアパレルとは -
2025/02/11
「あえて着ない」人が増加中 スーツ業界の復活はあるのか? -
2025/02/04
参入多いが難しいアパレルの多角化戦略、成功の秘訣は? -
2025/01/28
正しいTOC(制約理論)の理解 余剰在庫と欠品が激減する本当の理由!
この連載の一覧はこちら [61記事]
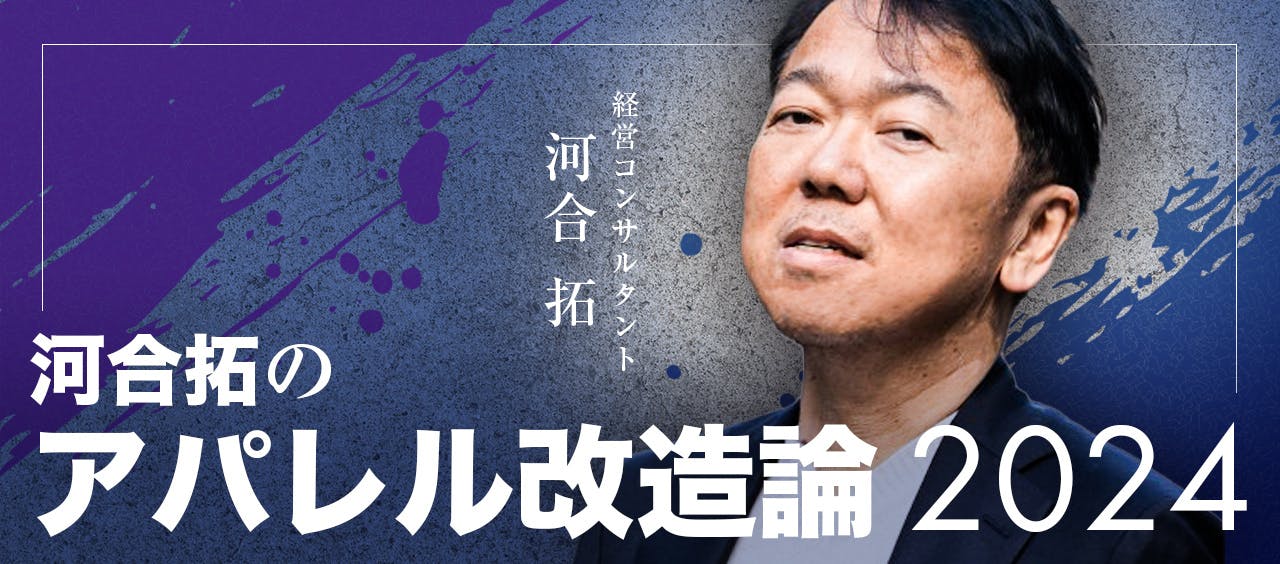
関連記事ランキング
- 2025-11-25ワコールを追い詰めた「三つの革命」
- 2025-12-02HUMAN MADE上場から考えるファッション産業の構造的限界
- 2025-11-27急拡大するリカバリーウエア市場を攻略する
- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価
- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ
- 2025-11-24間違いだらけのアパレルDX改革、根本から変えるべき「KPIの設計哲学」
- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度
- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?
- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは
- 2022-04-22ユナイテッドアローズ重松理名誉会長が語る、創業秘話とビームスを立ち上げた理由とは





 前の記事
前の記事

