製造コストは大人用と大差なし!新規参入、ワークマンが子供服市場で勝てる理由とは
ワークマンが子供服市場に参入するという。子供服というのは、非常に難しく、また特別だ。本日は、子供服市場の攻略方法とワークマンの子供服 workman kids(ワークマンキッズ)の行方についてうらなってみたい。なお、大体2~5歳ぐらいの幼児を「トドラー」とよび。 0歳~2歳までを「ベビー」、5歳~8歳までを「キッズ」と呼ぶ。この8200億円市場はワークマンは攻略することができるのだろうか?

6ポケットと子供服
子供服というのは、「6ポケット(シックスポケット)」と呼ばれ、子供の両親で2人、親それぞれの両親がそれぞれ2人ずつの4人で、合計6人の財布からお金がでる、典型的な商品だ。
したがって、特に高齢者である祖父母は、自分の孫に与える服を百貨店で買うことを好み、今でも百貨店で子供服を買うのだ。子供服が百貨店に強いのはそれが原因である。
購買に至るジャーニー(経路)を分析しよう。
まず、祖父母は「この服がよい」というデザイン上のこだわりも持ち合わせていないため、ほぼ百貨店の販売員の「押しの一手」で購買を決める。こだわりがあるとしたら、洗濯しても型崩れしないとか、色落ちしないという決め文句で購買を決定する。
仮に子供(=孫)を連れて買い物したとしても、子供は自分で好き嫌いがハッキリしないため、例えば店の内装が「ピンク」だとか、「ブルー」だとか、全体の色調で店を決め、選ぶときも服についたプリントや刺繍で「これがよい」と言う傾向があるため、最終決定者は祖父、祖母になることが多い。
これに対して、両親が子供に服を買う場合は、子供の成長は速く身長は毎年変わるため、百貨店のような高価な服は着させない。ショッピングモールなどで、安価でデザインも両親の好みのものを購買して子供に着させることが多いのだ。
ここからわかることは、①子供に服を選ぶ決定権はなく、②両親、祖父母の6ポケットからお金がでてきて、③販売員の「押しの一手」と「両親の好み」で子供の服が選ばれるということだ。なお、ある子供服アパレルでは、半分が贈答品となっている。
河合拓のアパレル改造論2024 の新着記事
-
2025/03/19
日本人の服がこの10年で「ペラペラ」になった本当の理由_過去反響シリーズ -
2025/03/12
ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ -
2025/02/18
ユニクロと競争せず“正しい”戦略ポジションを取っているアパレルとは -
2025/02/11
「あえて着ない」人が増加中 スーツ業界の復活はあるのか? -
2025/02/04
参入多いが難しいアパレルの多角化戦略、成功の秘訣は? -
2025/01/28
正しいTOC(制約理論)の理解 余剰在庫と欠品が激減する本当の理由!
この連載の一覧はこちら [61記事]
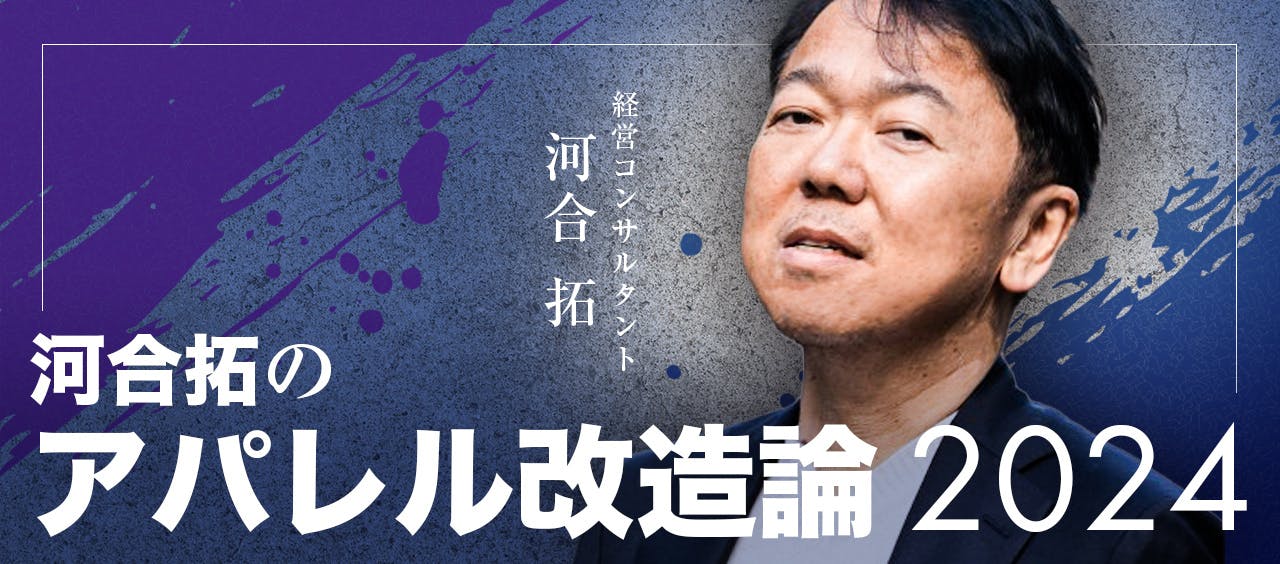
関連記事ランキング
- 2025-12-02HUMAN MADE上場から考えるファッション産業の構造的限界
- 2025-11-25ワコールを追い詰めた「三つの革命」
- 2025-11-27急拡大するリカバリーウエア市場を攻略する
- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価
- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ
- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは
- 2025-11-24間違いだらけのアパレルDX改革、根本から変えるべき「KPIの設計哲学」
- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度
- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?
- 2022-04-22ユナイテッドアローズ重松理名誉会長が語る、創業秘話とビームスを立ち上げた理由とは





 前の記事
前の記事

