コスモス、アオキが本腰、スーパーのオーケーも開始!「調剤」争奪戦のゆくえ
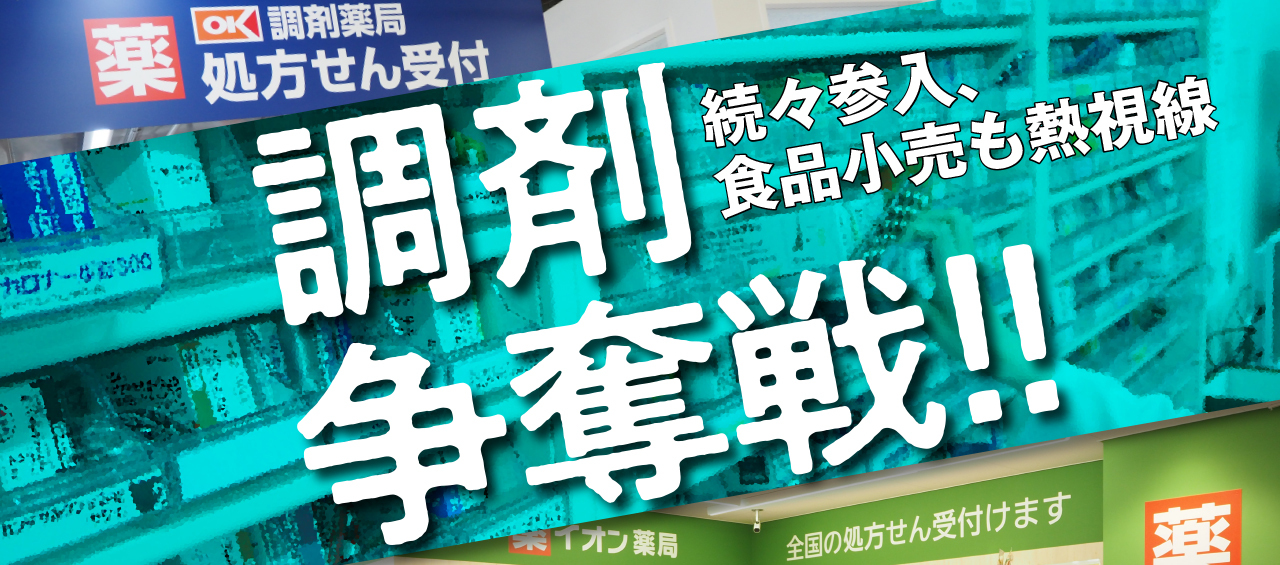
オーケーが調剤参入を決断、コスモス&アオキも事業強化へ
「オーケー薬局を始めます」──。今年5月、オーケー(神奈川県/二宮涼太郎社長)が同社ホームページ上で、2022年3月期の成長施策の1つとして「調剤薬局事業」への参入を明らかにした。その後8月1日、神奈川県横浜市にある「オーケー港北店」の2階部分に直営の調剤薬局第1号店となる「オーケー港北店薬局」を開業している。

本誌インタビューにおいて二宮社長は「オーケーを利用されているお客さまの総合的な買物の利便性を高めること」をねらいとして挙げた。すでに多くの競合他社を圧倒する競争力を有する食品売場に調剤薬局を加えることで、日常の食と健康を総合的に支えるフォーマットを創造しようというわけだ。
もっとも、ワンストップショッピングの利便性だけを追求するのであれば、テナントを誘致するかたちで調剤薬局を併設することもできる。現にSMの店舗内や、自社開発のNSC(近隣型ショッピングセンター)で調剤テナントを導入しているケースは珍しいものではない。しかし二宮社長は「運営ノウハウの蓄積、売場サイズや配置などを自社で自由に決定できること」などから、直営に踏み切ったという。
同様に、調剤ビジネスに食指を動かしているのがドラッグストア(DgS)だ。なかでも、これまで「食品強化型DgS」として注目を集めてきたコスモス薬品(福岡県/横山英昭社長)と、クスリのアオキホールディングス(石川県/青木宏憲社長:以下、クスリのアオキHD)が20年度の決算発表の場で口を揃えて「調剤強化」の戦略を発表したことは、小売業界に大きなインパクトを与えたと言えるだろう。
このうち、コスモス薬品は22年5月期に20~30店舗で調剤薬局の導入を計画。一方のクスリのアオキHDは22年5月期中に100店舗の開局、今後5年間で調剤併設率を70%(現在は50%超)に引き上げるという目標を掲げた(いずれも既存店への併設を含む数字)。
調剤ビジネスといえば、これまでは医療機関に近接するいわゆる門前薬局が大きなシェアを有していた。しかし、頻発する薬価改定や調剤報酬改定によって経営環境が目まぐるしく変化しており、さらにコロナ禍では医療機関の受診抑制の動きによって処方せん枚数も減少。とくに家族経営の中小薬局は淘汰の危機に瀕している。
そうした一方で、調剤市場での存在感を大きくしているのがDgSである。複数の医療機関からの処方せんを獲得できる環境の整備(いわゆる面分業)、薬剤師の採用状況に改善傾向が見られることなどを背景に、前述の食品強化型DgSも「調剤強化」を急ぐ状況になっている。
そこにオーケーのような食品小売、そして調剤薬局との共同出店や処方せん薬の受け取りサービス導入などを進めるコンビニエンスストアも部分的に参入。つまり門前薬局の“聖域”にさまざまなプレーヤーがなだれ込んでおり、まさに“調剤争奪戦”の様相を呈し始めているのだ。

調剤争奪戦!! の新着記事
-
2021/10/14
超アナログ市場にデジタル化の波 スタートアップ企業が進める調剤DXとは -
2021/10/13
全国消費者に聞く!調剤利用実態調査 デジタル対応、ポイント、速さ?調剤薬局に求めることとは -
2021/10/13
ドラッグストアのシェアはまだ 14%弱 細分化した調剤市場で成功する方法! -
2021/10/13
ワクチン接種も!米国の食品スーパーが調剤薬局を当たり前に備えている理由 -
2021/10/12
SM企業アンケート調査、驚きの結果に!「調剤ビジネスに参入するか?どうみているか?」 -
2021/10/12
調剤事業本格参入のコスモス薬品 その理由と参入効果、副作用とは?
この特集の一覧はこちら [12記事]
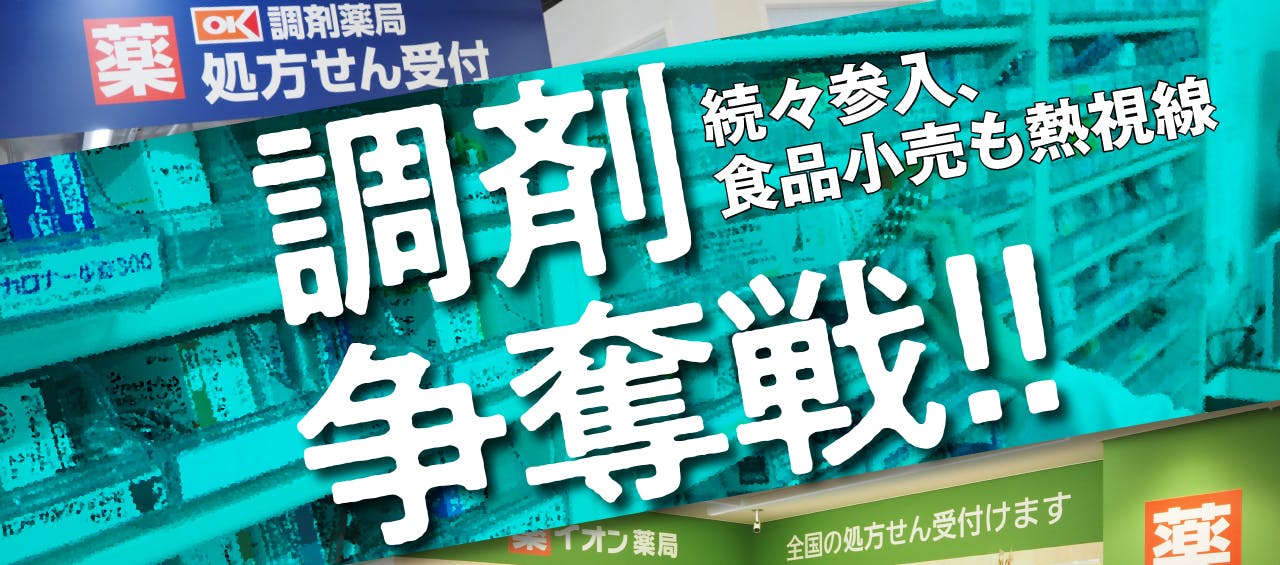
関連記事ランキング
- 2025-11-21速報!バロー関東1号店「横浜下永谷店」 オープン日の模様を徹底レポート
- 2025-11-21ベルクのディスカウントフォーマット「クルベ」、開店から2年超で見えた変化と進化
- 2025-11-26気づけば5店舗……クスリのアオキが出店増やす「スーパーのアオキ」の全容
- 2025-11-19上期絶好調のバローHD 関東進出直前、小池社長が明かした「攻め手」
- 2025-11-25オープンから2年超のクルベ その至近で競合するヤオコー、2店舗の関係から見えてきたこと
- 2025-11-21楽天撤退、ライフ参入 センター型ネットスーパー激動期へ
- 2025-11-17利益面に明暗……ライフ、U.S.M.H、アークスの中間決算を解説
- 2025-11-12ロピア進出機に阪神エリア随一の激戦地に 兵庫・尼崎エリア視察案内!
- 2025-11-22圧倒的集客力で激戦地を制圧!? 茨城タイヨーの「ビッグハウス」を大解剖!
- 2025-11-11意外にも”共存共栄”? 関西随一の激戦区・西宮の2エリアを徹底視察!





 前の記事
前の記事

