ユニクロ、開始から7年で明らかになった有明プロジェクトのいまとすごい成果
11月13日にファーストリテイリングの「LifeWear=新しい産業」説明会が開催された。事業成長とサステナビリティが完全に連動したビジネスモデルへの転換を目指す同社のいまを届ける説明会第4弾である。今回は、有明プロジェクトの観点から、サステナビリティと事業成長を連動させていて、今後どう進むのかについて説明している。
今回はこの説明会の内容を踏まえ、私の所見を加えた上でファーストリテイリングのサステナビリティと事業成長がどう連動しているのかについて論じてみたい。文責はもちろん100%私にあるが、文中でいくつか「類推」や「仮定」の元に書いた部分があるため、そこはわかりやすいように明記してある。

無駄なものを作らない、運ばない、売らない
説明会で最初に壇上にあがったのは、取締役グループ上席執行役員の柳井康治氏である。柳井氏のスピーチをかいつまんで解説する。
01年に社会貢献室発足で始まったファーストリテイリングのサステナビリティ活動は、04年に取引先工場の労働環境モニタリングを開始、07年には環境方針を策定、17年に主要縫製工場リストを公開、23年には古着販売のトライアルを開始という具合に、年々その活動の幅を広げ、事業との連動性も高まっている。
温室効果ガス(GHG)排出量のコントロールについては、自社領域(店舗やオフィスから出るGHG)では、23年8月期に対19年8月期比で69.4%もの削減に成功しており、30年8月期までにGHG排出量を19年8月期比で90%削減するという野心的な目標に対して、「オントラック」(スケジュール通り)で進んでいると説明した。
もっともGHG排出のコントロールが難しいと思われるパートナー先の海外生産工場については、3ヶ月ごとに対話し、工場、地域、国別の課題解決を進め、原材料に占めるリサイクル素材などの使用割合は、23 年の8.5%から24年には商品全体で18.2%へと大きく向上させた。
また、アングルを変えた話となるが、女性と外国人の管理職の割合は、なんと全社で約50%に届いているという。
最後に柳井氏は、本日のテーマである「無駄なものを 作らない、運ばない、売らない」ことで環境負荷の低減を実現するキーワードでスピーチを締めくくった。
河合拓氏の新刊、大好評発売中!
「知らなきゃいけないアパレルの話 ユニクロ、ZARA、シーイン新3極時代がくる!」
話題騒然のシーインの強さの秘密を解き明かす!!なぜ多くのアパレルは青色吐息でユニクロだけが盤石の世界一であり続けるのか!?誰も書かなかった不都合な真実と逆転戦略を明かす、新時代の羅針盤!
河合拓のアパレル改造論2024 の新着記事
-
2025/03/19
日本人の服がこの10年で「ペラペラ」になった本当の理由_過去反響シリーズ -
2025/03/12
ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ -
2025/02/18
ユニクロと競争せず“正しい”戦略ポジションを取っているアパレルとは -
2025/02/11
「あえて着ない」人が増加中 スーツ業界の復活はあるのか? -
2025/02/04
参入多いが難しいアパレルの多角化戦略、成功の秘訣は? -
2025/01/28
正しいTOC(制約理論)の理解 余剰在庫と欠品が激減する本当の理由!
この連載の一覧はこちら [61記事]
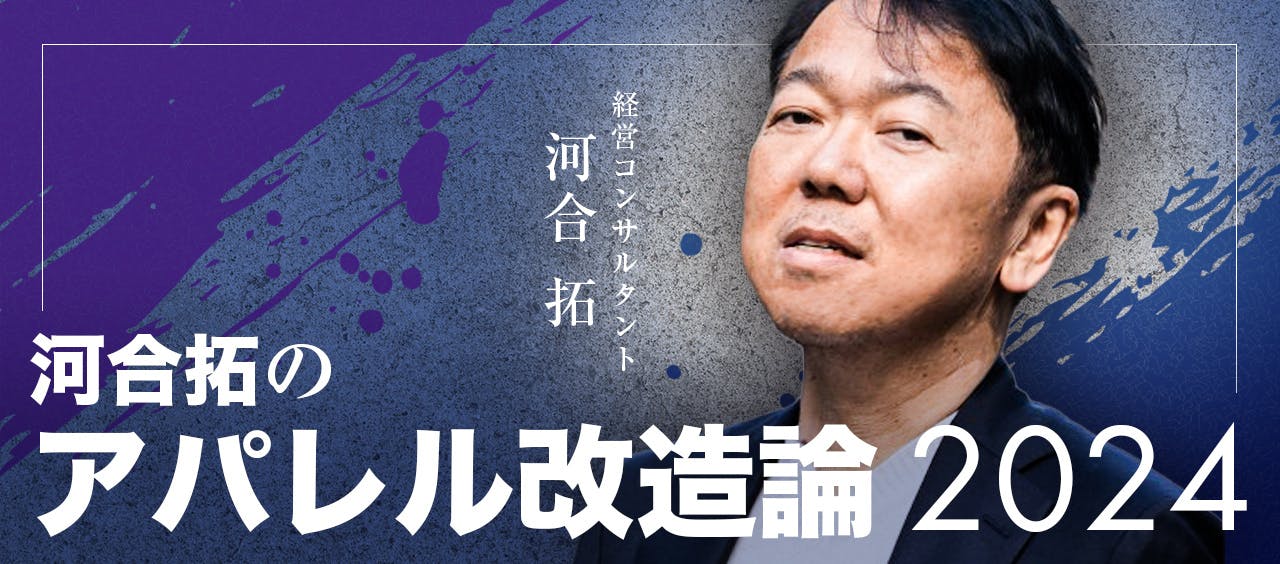
関連記事ランキング
- 2025-12-02HUMAN MADE上場から考えるファッション産業の構造的限界
- 2025-11-25ワコールを追い詰めた「三つの革命」
- 2025-11-27急拡大するリカバリーウエア市場を攻略する
- 2024-09-17ゴールドウイン、脱ザ・ノース・フェイス依存めざす理由と新戦略の評価
- 2025-03-12ユニクロ以外、日本のほとんどのアパレルが儲からなくなった理由_過去反響シリーズ
- 2024-09-03アローズにビームス…セレクトショップの未来とめざすべき新ビジネスとは
- 2025-11-24間違いだらけのアパレルDX改革、根本から変えるべき「KPIの設計哲学」
- 2025-11-26業態別 主要店舗月次実績=2025年10月度
- 2021-11-23ついに最終章!ユニクロのプレミアムブランド「+J」とは結局何だったのか?
- 2022-04-22ユナイテッドアローズ重松理名誉会長が語る、創業秘話とビームスを立ち上げた理由とは





 前の記事
前の記事

