トライアルはなぜ福岡の山間部でリテールDXを実現しようとしているのか?
リテールDX実現を図る3つの施設と2つの店舗

現在稼働している研究施設は大きく3つ。全国各社のメーカーや卸企業が集う「MUSUBU AI」、スマートショッピングカートなどデバイスの開発センターである「TRIAL IoT Lab」、ショッパーマーケティングの最適化をめざした店頭の販促企画検討やトライアル公式SNSの情報発信を行う部隊が在籍する「MEDIA BASE」です。
これら施設を開設するうえでは、個々での作業や研究のしやすさはもちろんですが、横連携の取りやすさという点にも非常にこだわりました。アメリカのシリコンバレーや中国の深圳などもベンチマークしており、あらゆる組織や機関の技術が結集することでさらなる発展を生むという、マイケル・E・ポーター教授が提唱する「クラスター」の形成を期待しています。宮若にさまざまな人材が集まることでクラスター効果が発生しイノベーションが起きる。そんなコミュニティをめざしているのです。
イノベーションを起こす新しい「集合体」をつくるために
ここでクラスター効果についてもう少し詳しく説明しておきましょう。
クラスター効果とは、特定部門の関連企業や、供給業者、サービス提供者、大学・自治体などが一定の地域に集積することで、競争と同時に協調が生まれ、「産業の生産性向上」「イノベーション誘発」「新規事業展開」が生まれることを指します。技術面のインフラやお客さまのニーズから生まれる知識的なデータの集積から幅広い横のつながりを形成し、そこからイノベーションを発生させる新しい「集合体」がつくり上げられる、というわけです。
言い換えれば、一つの産業領域を従来の型にとどまらない「新しいエコシステム」を形成することで活性化させる、要するに「共創」を本当の意味で実現したものと言えるでしょう。
次回はこの「共創領域」のさらに拡大をめざす、われわれの今後の動きについて詳しく触れていきます。
Retail AI 永田洋幸の「リテールDX・新章」 の新着記事
-
2024/06/27
トライアルが「日本のシリコンバレー」を福岡に本気でつくりたい理由 -
2024/05/16
トライアルはなぜ福岡の山間部でリテールDXを実現しようとしているのか? -
2024/03/29
Retail AI永田洋幸CEOが”出展者目線”で分析する「NRF2024」の潮流とは? -
2024/02/12
トライアル×九州大学病院が立ち上げた「ライフケアテックコンソーシアム」とは何か? -
2024/02/08
トライアル×NTTのタッグで「発注業務の自動化」を真っ先にめざす理由 -
2024/02/06
トライアルグループが「顔認証システム」の開発・導入に本腰を入れる理由
この連載の一覧はこちら [6記事]
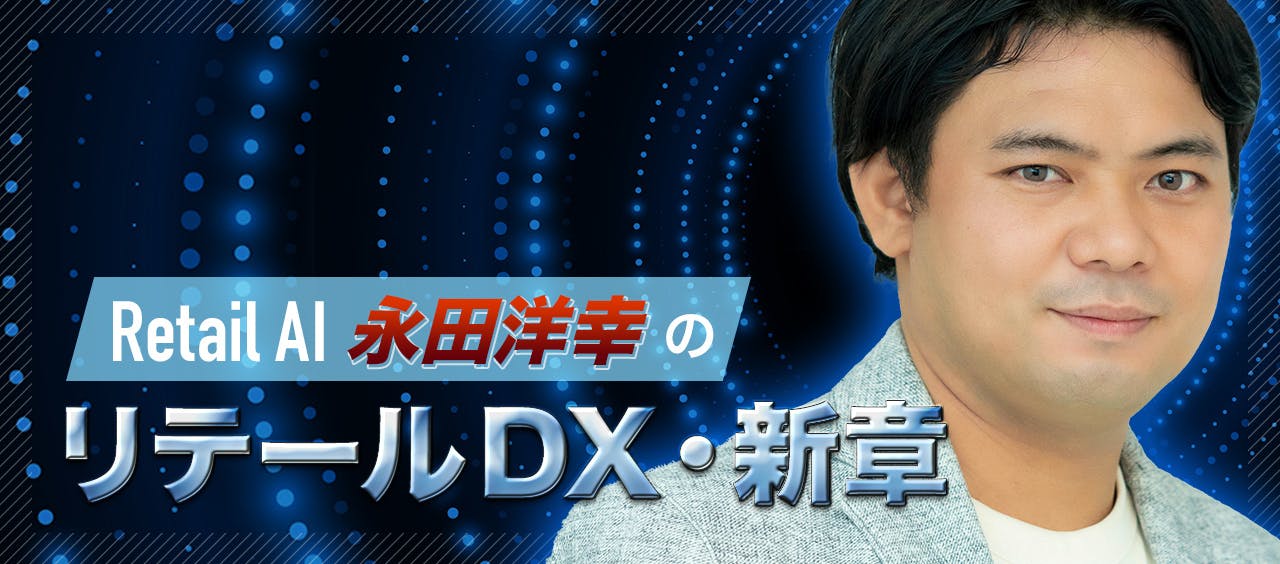
トライアルの記事ランキング
- 2025-11-07ついに東京23区進出!「TRIAL GO西荻窪駅北店」の売場を速報
- 2025-11-28トライアルグループの新フォーマット1号店「トライアル西友花小金井店」の売場を速報!
- 2025-11-11NEC、トライアルらが「流通エコシステム」開発に着手 26年までに実装めざす
- 2025-11-06トライアルが西友の買収を完了 徹底解説!結局、何がどう変わるのか?
- 2025-11-12週刊コンビニエンスストアニュース 「TRIAL GO」がついに東京23区に出店!
- 2025-11-14福岡視察の必見エリア!福岡市西区の注目店舗を完全ガイド!
- 2023-03-28トライアルの”都心部攻略”の成否を占う!? 「TRIAL GO 今泉店」売場レポート
- 2024-05-10トライアルの小型フォーマット「TRIAL GO」の全貌とは
- 2025-11-14価格+αの価値競争が激化!福岡市博多区周辺の注目店舗&視察ポイント
- 2025-04-29西友買収のトライアル、そのビジネスモデルの強さを小売ウォッチャーが解説!





 前の記事
前の記事

