人口減少時代、スーパーの定番手法は間尺に合わなくなる!いまやるべき3つの具体的投資とは
“間尺”に合わなくなるSMの定番手法
食品スーパー(SM)業態が日本に誕生してから約70年が経とうとしている。生鮮食品のほか日配品、加工食品など、食卓に並ぶ食材を提供する重要な役割を果たしているのがSMである。われわれの生活に浸透し、不可欠なインフラとして機能している。
振り返れば、SMについてはこれまで数々の運営手法、ノウハウが開発されてきたが、多くは人口が増加していた時代に編み出されてきたものだ。つまり需要や市場が拡大することを前提にしているといってもいい。
たとえばマーケティング分野、もしくは価格政策の「ロスリーダー戦略」。特定の商品において採算を度外視した低価格を設定して集客、大量販売する方法である。効果を狙って価格弾力性の大きいアイテムを選び、目当てに来店したお客がほかの粗利益率の高い商品を買うことで店全体の利益に結びつける。
人口が年々、増えている時期には、市場全体の需要が拡大しているため有効で、繰り返し行うことにより、着実に大きく利益を上げることができた。近年はEDLP(エブリデー・ロープライス)に移行するケースが少しずつ増えてはいるものの、かつての成功体験から、今もハイ&ロー価格政策を主力にしている企業は多い。
精肉、鮮魚などの生鮮食品や、弁当、揚げ物といった総菜の「インストア加工」も同様だ。売上高が伸長している時期には多くの人手を投入することもできた。一方では鮮度を最優先するため、最終消費地に近い場所にある店内で商品のカットや調理を行ってきたという面もある。
しかし冷凍・冷蔵、加工技術、物流分野ではコールドチェーンなどの進化はめざましい。消費者の家にある冷蔵庫も変化しており、同じサイズであっても大容量化するほか、鮮度を保つためのさまざまな新機能が次々と搭載されるようになっている。
SMでは、家庭での優れた保存環境を想定した商品開発、提案があってもよさそうに思うが、今も昔ながらのインストア加工にこだわる企業が多いのが現状である。SMの定番ともいえる、これらの手法は今も現役だ。しかし今後、人口減少が進み、さらに加速することになれば、いずれもビジネスの間尺に合わなくなり、やがて通用しなくなることは十分考えられる。
10年後のリアルに備えよ 人口減少と闘う! の新着記事
-
2021/06/14
人口減・少子高齢化で消費はこう変わる!食品小売業がとるべき2つの戦略とは? -
2021/06/14
コスモス薬品創業の価格激烈エリアで、売上8年で70%伸ばしたスゴイローカルスーパーの戦略 -
2021/06/14
人口急減、高齢化率44.4%の商圏で業績伸ばす、三重の主婦の店 電子マネー比率6割の謎! -
2021/06/11
1フロアまるごと無償提供?人口減少地域で存続を模索するイズミヤがとった秘策とは -
2021/06/11
地方より都市部に影響大⁉ 2040年までの人口減少の影響を解説 小売とるべき対策とは? -
2021/06/11
生鮮含め衣食住揃う300坪未満の小型店が人口減の町・村の救世主?DCMニコットの戦略
この特集の一覧はこちら [8記事]
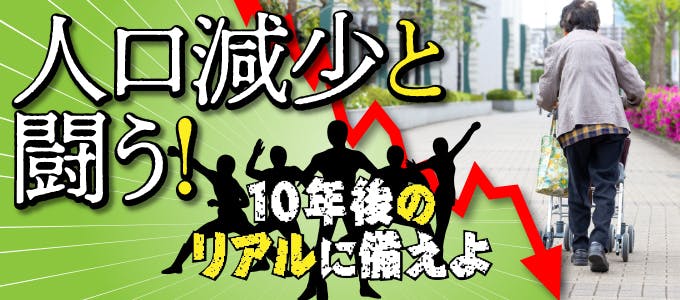
関連記事ランキング
- 2025-11-21速報!バロー関東1号店「横浜下永谷店」 オープン日の模様を徹底レポート
- 2025-11-21ベルクのディスカウントフォーマット「クルベ」、開店から2年超で見えた変化と進化
- 2025-11-26気づけば5店舗……クスリのアオキが出店増やす「スーパーのアオキ」の全容
- 2025-11-19上期絶好調のバローHD 関東進出直前、小池社長が明かした「攻め手」
- 2025-11-25ウエルシア、コスモス、アオキ、薬王堂……フード&ドラッグ東日本主力4社の戦略とは
- 2025-11-25オープンから2年超のクルベ その至近で競合するヤオコー、2店舗の関係から見えてきたこと
- 2025-11-21楽天撤退、ライフ参入 センター型ネットスーパー激動期へ
- 2025-11-17利益面に明暗……ライフ、U.S.M.H、アークスの中間決算を解説
- 2025-11-26ウエルシアHDの新フォーマット「ドラッグ&フード」 売場づくりの全貌を大解剖!
- 2025-11-12ロピア進出機に阪神エリア随一の激戦地に 兵庫・尼崎エリア視察案内!
関連キーワードの記事を探す
気づけば5店舗……クスリのアオキが出店増やす「スーパーのアオキ」の全容
「ドラモリ」が価格競争の台風の目に? フード&ドラッグ激戦区・宮城県名取市を現地調査
ウエルシア、コスモス、アオキ、薬王堂……フード&ドラッグ東日本主力4社の戦略とは
ウエルシアHDの新フォーマット「ドラッグ&フード」 売場づくりの全貌を大解剖!





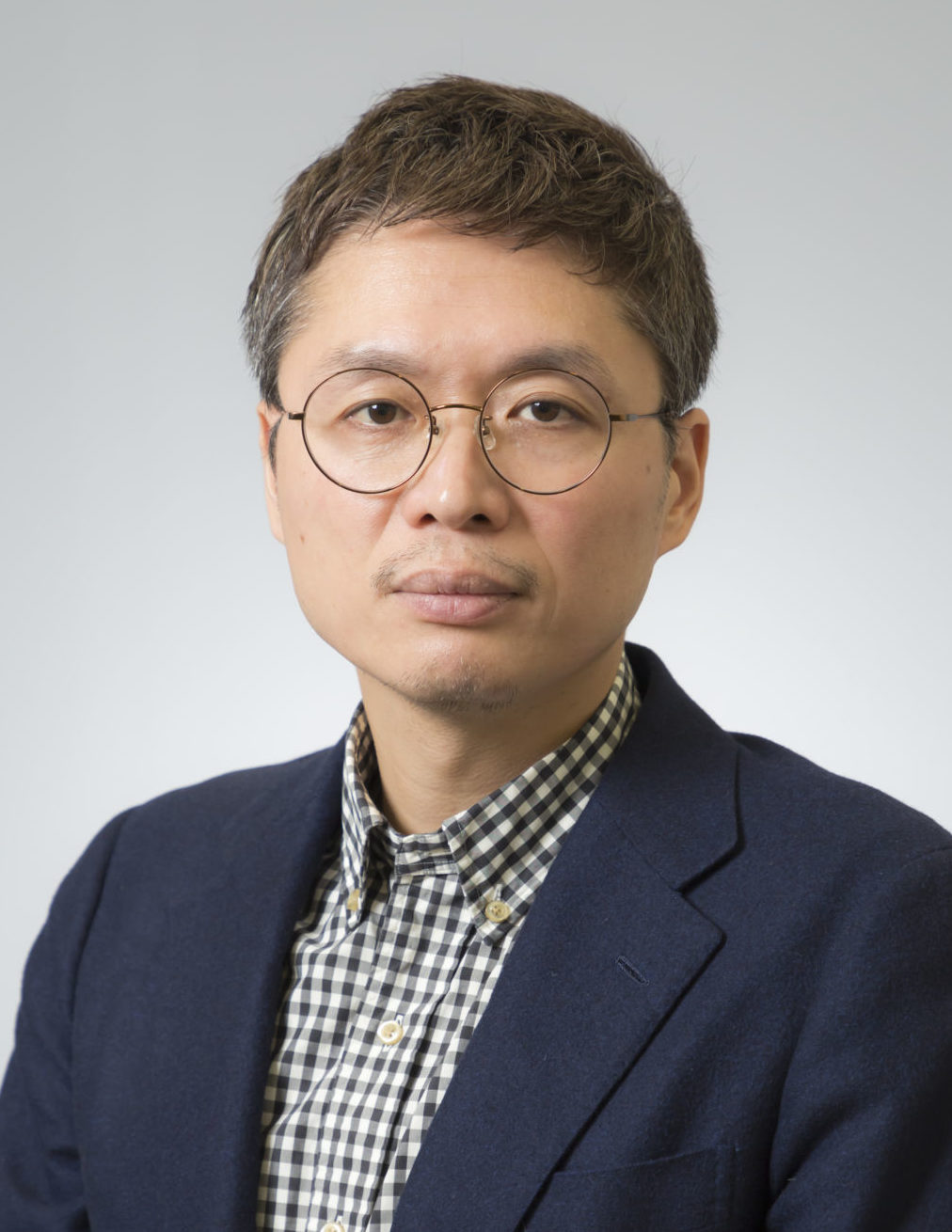
 前の記事
前の記事

