食卓に並ぶ日は?日清食品HDが挑む“未来のステーキ”、培養肉の現在地
「培養ステーキ肉」に立ちはだかる幾重もの壁
22年には、作製過程に使われる試薬をすべて食用可能な素材に置き換え、実際に試食可能な培養肉を完成させた。ちなみに、試食用の培養肉は食用色素で赤身肉のような色味をまとっているが、赤血球を含まない培養肉そのものは本来、白っぽい見た目をしているという。
24年8月には、培養した脂肪組織を組み合わせることで、より畜産の牛肉に近い見た目をもつ約30gの培養ステーキ肉の作製に成功したことを発表した。最新の進捗状況を問うと、「重さだけでいえば90g程度まで到達した。100gをひとつの目標に掲げていたが、今年度中には達成できるだろう」と、古橋氏は経過を語った。

もっとも、食べることができ、なおかつ味や見た目、食感まで再現した培養ステーキ肉を実現するまでの道のりは、まだまだ長い。「22年の試食の時点では、歯ごたえも味も感じられた。ただ、残念ながら肉の味ではない。材料としては牛肉に近いものを使っているが、脂肪分と血液成分がない状態ではあまり肉らしい味がしないようだ」(古橋氏)
培養ステーキ肉を商品化まで漕ぎつけるには、コストや量産といった壁も立ちはだかっている。「現状は、細胞を培養するためのデバイスから自前でつくっているような状況で、手作業も多い。効率良く細胞を増やすためにも、細胞を組織化した後に大量生産するためにも、それに適した手法とデバイスが必要になる。まだ改善すべき点は多々存在する」と、古橋氏は現状の課題について言及した。
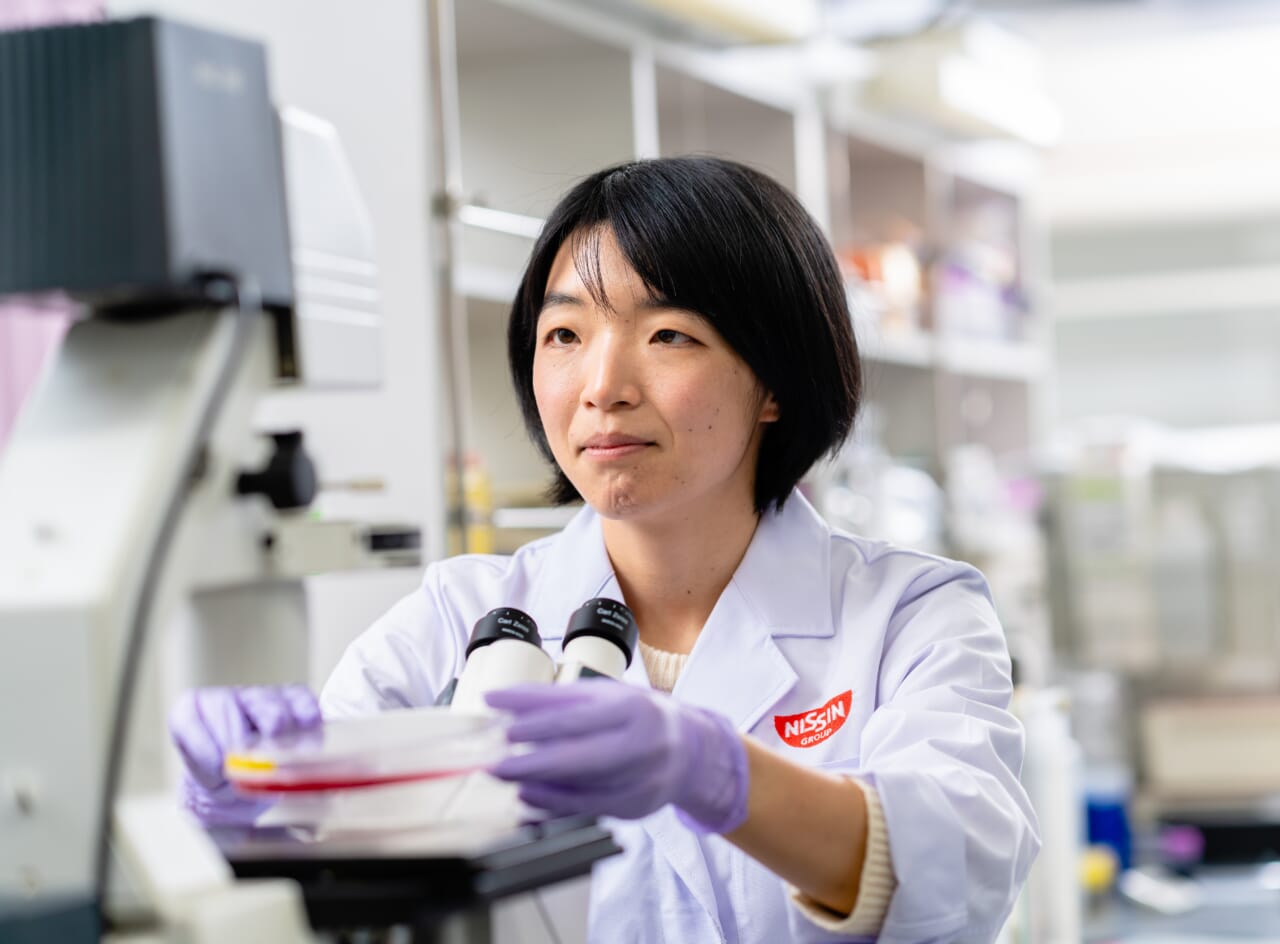
市場に流通するまでには、さらに高いハードルがある。培養肉は、従来の食品にはない新技術を用いて製造されるため、まずは食品としての安全性審査や品質表示に関する基準が定められなくてはならない。
日本のスーパーマーケットの精肉売場に「培養ステーキ肉」が並ぶ未来は、まだまだ先になりそうだ。しかしながら、日清食品HDは、当初掲げたゴール「24年度中に幅7cm×奥行7cm×厚さ2cm、約100gの培養ステーキ肉の基礎技術確立」に対して着実に成果をあげている。
古橋氏は、「今後は、基礎技術と応用技術の間にある半基礎技術のような部分、つまり、味や見た目、食感、効率的な生産手法の確立といった部分を磨いていく」と、次なる目標を語った。



