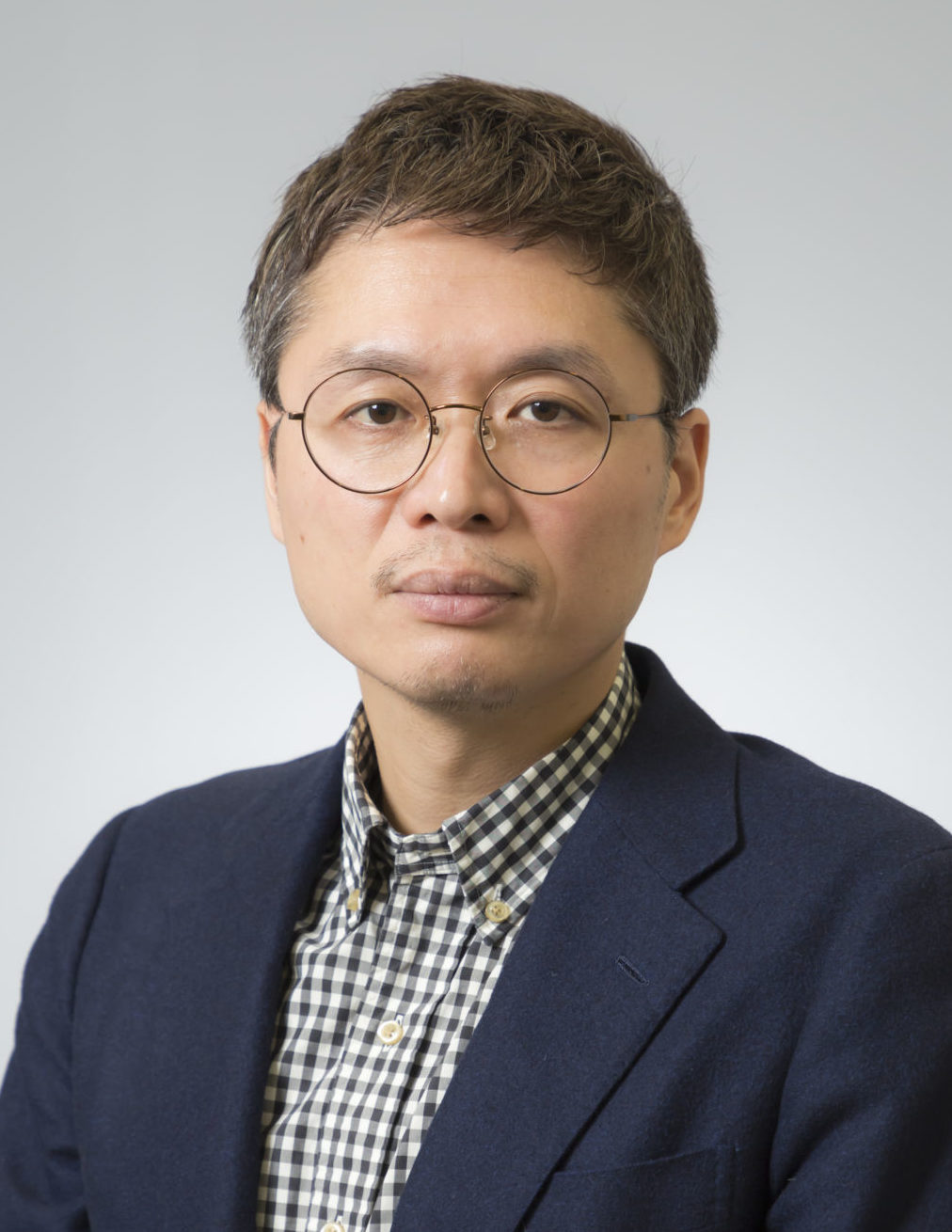ヤマダイ代表取締役社長 大久保 慶一
少量多品種のものづくりで独自の道を築く
創業70周年を迎えた2018年、基幹商品であるノンフライ麺の「凄麺」ブランドをより強化し、品質向上に注力するため、新工場増築に踏み切ったヤマダイ(茨城県)。ブランド誕生から17年、今なお成長し続ける要因は何なのか。そして今後、同社はどう歩んでいくのか。大久保慶一社長に聞いた。
コモディティ化させない!「凄麺」ブランドの強み
──2001年に誕生した「凄麺」ブランドが好調です。

大久保 おかげさまで、発売以来、じわりじわりと露出が上がっていき、お客さまから高い評価をいただいています。
近年、商品の「コモディティ化」がナショナルブランドメーカーの間でも問題になっていますが、そうなるには相応の理由があると思っています。絶え間なくブラッシュアップを行い、お客さまから信頼を得られるような取り組みを続けていけば、コモディティ化はある程度抑えられるのではないでしょうか。
「凄麺」ブランドは、まさにそういう商品づくりを行い、売り方においても“数字ありき”ではなく地道に取り組んできました。先に数字があると、どうしても無理な販売の仕方をしてしまい、結果、メーカー自らが商品の価値を下げてしまいます。ですから、当社の商品は急速に大きく伸びないけれど、堅調に推移しているものが多いですね。
──昨年、シリーズ最初の商品である「凄麺これが煮玉子らーめん」の発売日にちなんで、10月29日を「凄麺の日」として、一般社団法人日本記念日協会に認定されました。話題づくりもユニークですね。
大久保 ブランド強化策のひとつです。オリジナルキャラクターや新ロゴをつくり、キャンペーンなどを実施しました。あわせて「凄麺の日」を記念した試食販売イベントも開催し、私も店舗を回って応援を行いました。
店頭に立って感じたのは、少子化と高齢化が進み、単身世帯が増えているということ。70代の女性と話をしたのですが、私どもの商品をよくご存じでした。一人暮らしで、「凄麺」を食べるのが楽しみと言われ、この値段でこれだけのものが食べられるなんてうれしいとお褒めの言葉もいただきました。
インスタントラーメンには、手頃な値段で買えるという価値がありますが、今の生活者にとってはそれだけでなく、もっと重要な役割もあるような気がしますね。
店頭でのプロモーションを第一に考える
──全国各地の店舗に足を運んでいるそうですが、昨今の消費者行動をどうとらえていますか。
大久保 商品を供給する側と消費する側との間にギャップが起きていると思います。お店には絶えず新商品が置かれていますが、お客さまはそれほど求めていないのではないでしょうか。情報も氾濫し、何を購入していいのかわからない状態に陥っているように感じます。
──ギャップを埋めるために、どのようなことに取り組んでいますか。
大久保 やはり現場、すなわちお客さまに商品を購入していただく店頭でのセールスプロモーションを第一に考えています。小売業さまの協力をいただいて大量陳列を行ったり、店頭での試食販売をしたり。どちらかというと泥臭い施策ですが、それらを継続することで、お客さまに納得して買っていただくことを大事にしています。
──大量販売を前提としたマーケティングはしない、ということですね。
大久保 大量販売を継続的に行おうとすると、商売には波がありますから、どうしても無理な販売手法を取ってしまいがちです。そうすると、メーカー側が伝えたい価値が、お客さまに違うかたちで伝わってしまうことになると思いますね。
試食販売などでお客さまと話をすると、予期しない答えが返ってきて驚きます。インスタントラーメンは若い人が買うとか、生活者は新しいものを求めているとかいわれますが、そうとも言い切れないのです。かつてはインスタント食品の購入は、60歳を過ぎるとがくんと落ちたものですが、今は違います。
──ボリュームゾーンの若年層をターゲットにしたマーケティングを行っている競合他社は依然として多いです。
大久保 他社さんには他社さんの考えがあるのでそれでよいのだと思いますが、当社としては、特定の年齢層にだけ偏るのはよくないと思っています。単品で大量に売るよりも、たくさんの種類でもって量を売るというのがヤマダイの考え方。バラエティに富んでいることの価値を大事にしていきたいと考えています。
実際、「凄麺」ブランドは期間限定商品を含めると30品以上を展開しています。どんなにおいしいものでも、同じものを食べ続けていれば、やがて飽きがくる。それを防ぐには、ブランドの幅を横に広げること。そうすることで、息の長いブランドになるのではないでしょうか。