物価高でPBに変化と進化の兆し 「買いたくなる」商品の条件とつくり方とは
共通PBに留め型商品、中小でも独自商品は可能!
ただし、生産ロットを確保するための一定の売上規模が必要であることに加え、自社で製造リソースを抱えなければいけないなど、SPAの参入障壁は高い。また、さまざまなカテゴリーでオリジナル商品を展開するためには、それに対応したインフラを整備する必要があり、ラインアップを増やそうとすればするほど取り組みの難易度は上がっていく。すべてのチェーンがSPAに取り組めるわけではない。
他方、物価高の中、とくに中堅・中小チェーンでその存在感を大きくしているのが、CGCグループ(東京都/堀内淳弘社長)が展開する共通PB「CGC商品」だ。本特集では、規模の異なるCGCグループ加盟企業2社の売場を調査しているが、両チェーンとも、自社の企業規模を踏まえたうえでCGC商品をうまく活用している様子が垣間見えた。
名だたる大手メーカーが製造を担うCGC商品は、品質が優れている一方で爆発力のある安さはなく、これまではPBというよりもNBに近い面があった。だが、あらゆるモノが値上げに向かうこの局面の中においては、相対的に値ごろ感が創出され、着実に支持を拡大しているようだ。品揃えや売価設定も加盟企業の裁量で決定されているようで、中堅・中小にとってはなくてはならない存在となっている。
そのほか物価高騰下の商品開発の手法として、留め型商品にも注目が集まっている。留め型商品とは、メーカーが特定の小売業に向けて製造する商品のことを指し、一般的なPBと比較して、「小ロットで発注可能」「発売までのリードタイムが短い」などの利点がある。
食品小売のPB・留め型商品の企画・開発・製造をサポートするukka(東京都/谷川佳社長)によれば、最近は、定番はPBでラインアップしながら独自性を打ち出す商品を留め型で商品化する、といった活用事例もあるという。コスト上昇で調達・開発が難しくなる中では、留め型による“小回りの利く”開発も検討の余地がありそうだ。
本特集で実施している消費者調査では、日頃購入する食品をNBからPBに切り替える、ブランドスイッチの動きも確認されている。物価高は確かに厳しいものの、PBにとってこの状況は商品を手に取ってもらう絶好のチャンスでもある。ここで商品の価値を正しくお客に伝えることができれば、リピート・定着も期待できるだろう。各社はどのような価値を追求し、物価高時代でも「買いたくなる商品」を開発しているのか。本特集にはそのヒントが詰まっているはずだ。
次項以降は有料会員「DCSオンライン+」限定記事となります。ご登録はこちらから!
「買いたくなるPB」のつくり方 の新着記事
-
2025/03/29
PB開発競争は成熟期に突入? 専門コンサル企業が提言するPB進化の方向性 -
2025/03/29
商圏拡大が商品進化を促す? ロピアのPB戦略最前線とは -
2025/03/28
物価高で存在感急拡大! 加盟店売場から見た「CGC商品」の底力とは -
2025/03/28
最強DS「ラ・ムー」にもインフレの波……“カテゴリー深掘り”で現状打破へ -
2025/03/27
組合員の“推し”を集める! 日本生協連のPB「コープ商品」の最新戦略 -
2025/03/27
簡便・即食、健康志向…… 業務スーパーのPBに大変化の兆し!
この特集の一覧はこちら [10記事]





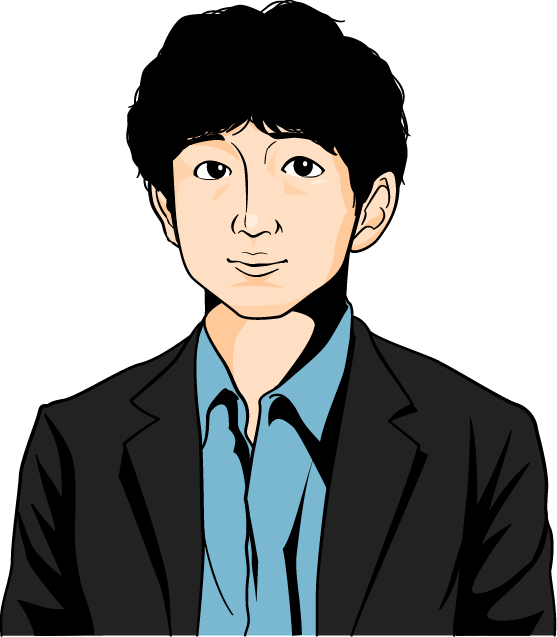
 前の記事
前の記事

 売上高1兆円超え!イオンのPB「トップバリュ」はなぜ快進撃を続けるのか
売上高1兆円超え!イオンのPB「トップバリュ」はなぜ快進撃を続けるのか