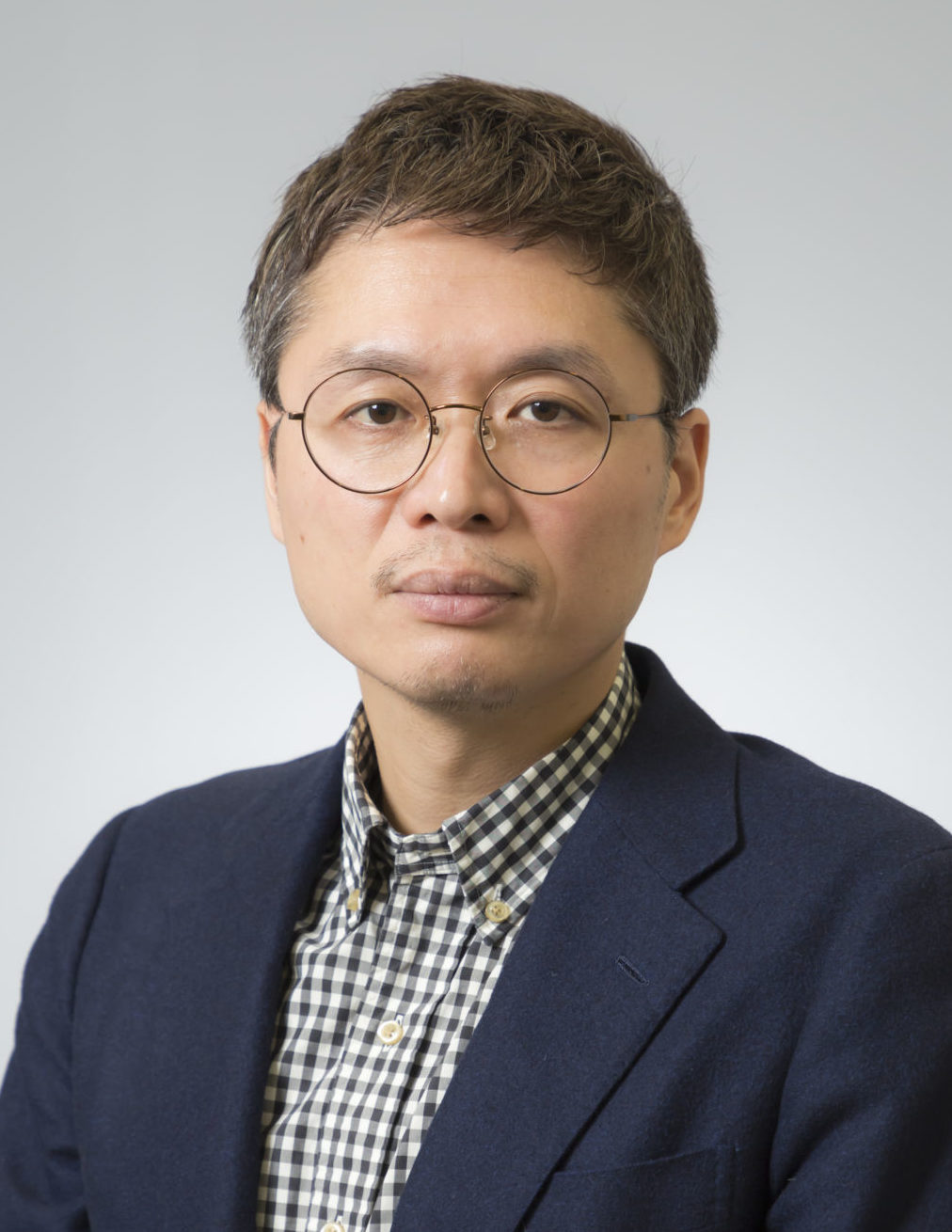顧客時間・奥谷孝司氏、「DXとはお客と一生つながり続ける覚悟を持つこと」の真意とは
小売業は「地に足のついたDX」を
──現在の小売業界に対するメッセージをお願いします。
奥谷 大きく2つあります。1つ目は、小売業は地に足のついたDXをやるべきであるということ、そしてそのためにはトップのDXへのコミットメントが必要だということです。
私は「量の経営」と「質の経営」と呼んでいますが、荒っぽく言ってしまうと、お客さまのことは知らないが、商品を仕入れて店舗に並べておけば売れていく、というのが旧来の「量の経営」です。
リアルでの事業が強い企業が、ECをはじめとしたデジタルに取り組む場合、デジタルがリアルを超えることはまずありません。そうすると、「投資ばかりがかかって儲からない」という考えになりがちです。
しかし、お客さまと直接つながってコミュニケーションがとれるのはデジタルです。前述のとおり、デジタルに取り組むということは、「24時間365日、お客さまとつながる覚悟を身につける」ということです。
たとえば、LINEのビデオ通話でお客さまからの連絡を受け、お客さまの目の代わりになって、売場で商品を選んだり、商品を取り置きするサービスをやるとしましょう。そのようなビジネスは1日当たりの売上高は微々たるものかもしれません。ですが、そうした取り組みが「質の経営」につながっていくのだと思います。
必要なのは、デジタルを販路ではなく、お客さまとの繋がりとして考えることです。現在、「量の経営」がうまく回っている小売業、たとえば食品スーパーやホームセンターなどは、そうした方向にシフトしていくのがとよいと思います。
──2つ目はどのようなことでしょうか。
奥谷 2つ目は、直近でニューヨークに行って感じたことになります。それは、DXを進めるうえではテクノロジーを使いこなすことを前提に、「買物価値」を上げなければならないということです。
リテールテックをお客さまが受け入れるというキャズムはもう超えたと私は思っています。米国には「Amazon Go」 をはじめ優れたリテールテックが集結した店舗がありますが、それらのお店の大半はお客さまが求める買物価値が乏しいように思います。
一方で「Amazon Fresh」は、Amazon Goの反省を活かしてリテールテックを活用しながらも買物価値を高める努力が垣間見れました。たとえば、PB商品や総菜を充実させることで買物価値を上げています。それらは、買物価値が元々高いホールフーズ(Whole Foods Market)のような企業から学んできたわけです。
ウォルマート(Walmart)のBOPISも平日は常時混んでいますが、ECをやっていないトレーダー・ジョー(Trader Joe’s)も客足は負けていません。そうした光景を目にして考えたのは、原点に帰らなければいけないということです。人々にとって大切なのは、買物価値であり、技術レベルはどうでもよいのです。
たとえばウェグマンズ(Wegmans)はインスタカート(Instacart)と連携し、店舗出荷型の配送などに取り組んでいますが、店舗に行くと、優れた商品があり、売場がきれいであり、品質基準も優れている、といったことをまず感じます。ウェグマンズのテクノロジーが優れているとは誰も思わないわけです。
お客さまにとって“程よいテクノロジー”とは何なのか。そういったことを考えながら、これからの時代はDXを行っていく必要があると思います。