サンドラッグ 全社で男性育業を推進 復職フォローの仕組みで育業の取得率アップ
安心して育業できた要因は社内の理解と上司のフォロー

同社には、「男性でも育業するのが当たり前という空気感がある」と話す営業部の日向貴明部長代理。とはいえ、2021年11月の第一子誕生のときには、初めての不安があったという。給与に関することや職場復帰などをはじめ、当時のゾーンマネージャーという役職から、引き継ぎによる部署内での業務の負担増などの心配は絶えなかったという。
社内のイントラネットで、育業の情報を確認したり、相談窓口で話を聞くようにした。なによりも安心できたのが、上司からの声がけのフォローだった。業務の引き継ぎ期間も十分に確保してもらえるなど、納得できる対応に安心感をもったという。
そのときはすでに、社内の育業への理解も浸透しており、育業しやすい環境が整っていることも実感できた。
育業のメリットはライフ・ワーク・バランスの向上
第一子のときは2カ月、第二子誕生の2024年1月には3カ月育業した日向部長代理。「出産時の母体に与えるダメージや子育てが想像以上に大変であることを実感しました」と話す。第二子のときは、第一子のときよりも、さらに、育業しやすくなっていたという。第一子のイヤイヤ期と重なったこともあり、3カ月とより期間を長くしたことは正解だったと語る。「妻に、あなたがいなかったら乗り越えられなかったかも」と感謝されたといい、「子供の成長は早いので、一緒に過ごす時間を持てたことは、何事にも変えられない。貴重な時間を共有できたことが、とても幸せでした」と、育業の感想を語る。子供との絆が深まり、夫婦の相互理解も進んだことで、仕事に対する意欲も高まった。同社では、男性の育業期間は平均で約3カ月、中には1年以上というケースもある。
職場復帰を円滑にする独自の仕組みを整える
職場復帰に関しても、同社はフォロー制度を整えている。職場への復帰前と復帰後に上司や人事部の相談窓口への確認、相談する機会が設けられている。育業期間中の業務に関する確認や復帰後の業務の確認を経て、復帰。その後1カ月ほどは、以前のように業務に対応するための「ならし期間」が設けられている。
「私の場合は、第二子のときの復帰のタイミングで、いまの部長代理に昇進をしました」と日向部長代理。そのための業務の確認や引き継ぎなど、無理なく進められたことから、なんの支障もなく、業務に対応することができた。
サンドラッグの「育業」への積極的な体制づくりは、ライフ・ワーク・バランス推進の一環として、働く従業員の満足度向上が図られるだけでなく、企業価値向上につながる取組として注目される。
「育業」とは

育児は「休み」ではなく「未来を育む大切な仕事」
「育業」とは育児休業の愛称です。東京都は、育児は「休み」ではなく「大切な仕事」と考える愛称「育業」の理念を浸透させ、多様な主体と連携して、育業を社会全体で応援する気運醸成に取り組んでいます。
育業ベストエピソード決定!
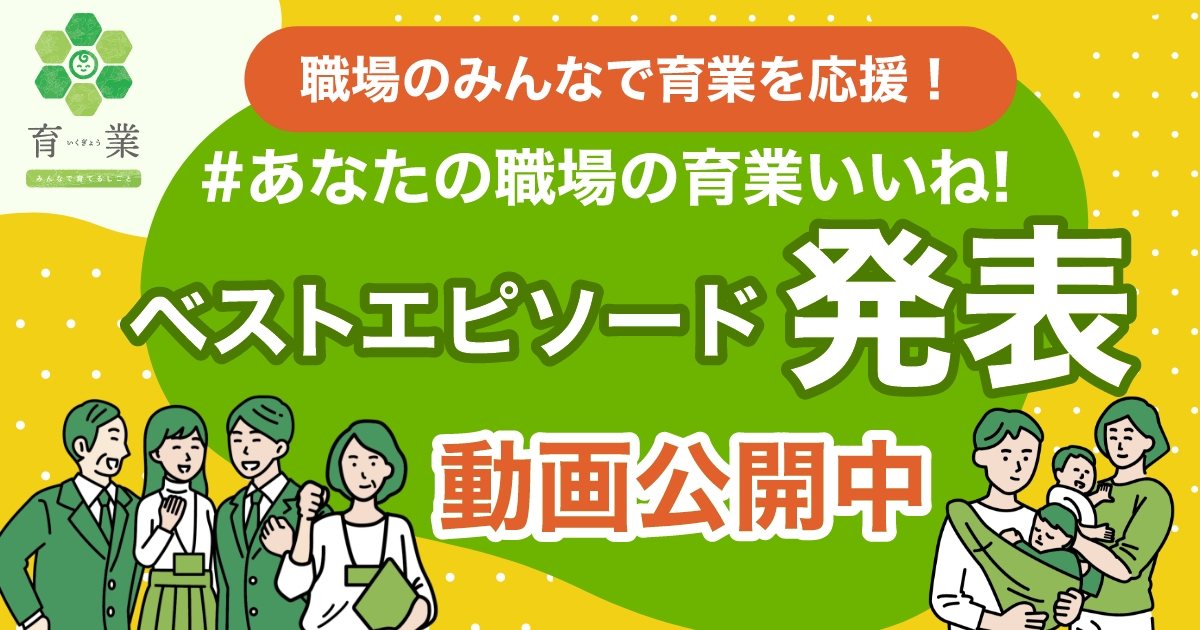
育業を後押ししてくれたエピソードを募集し、投票で選ばれたエピソードをもとに動画を制作しました。動画を広く発信することで、育業いいね!と思える職場の雰囲気づくりにつなげていきます。詳細はこちら
人事担当者必見!管理職向け「育業」研修教材を公開中!
~「育業」研修、はじめませんか?~
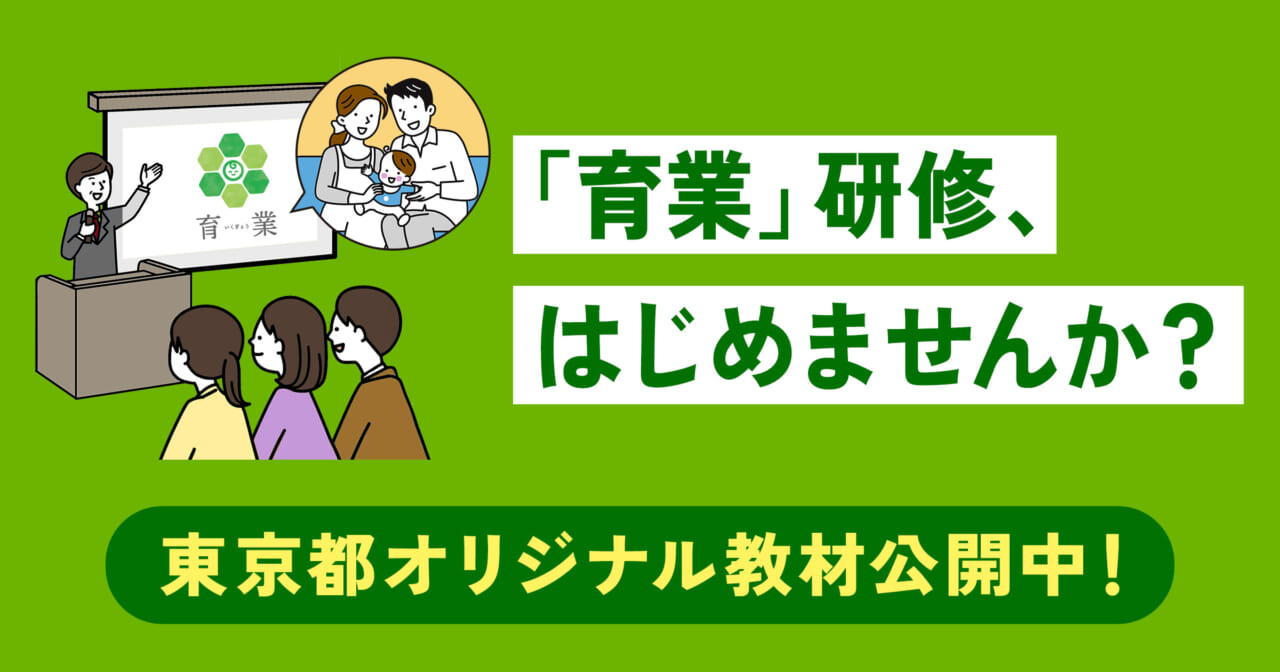
令和6年11月に企業と連携して管理職向け「育業」出前研修を実施し、研修で活用した教材を公開中です。育児・介護休業法の改正により、令和7年4月1日以降、300人超の企業に男性の育児休業取得状況の公表が義務付けられます(現在は1,000人超の企業)。新たに公表対象となる企業など人事担当者の皆様におかれましては、社内研修等でぜひご活用ください。
詳細はこちら
※1:東京都が2022年に公募で定めた育児休業の愛称。
※2:『プラチナくるみんマーク』とは、次世代育成支援対策推進法に基づき子育てをサポートする企業として認められる『くるみん認定』を受けた企業のうち、「男性の育児休業取得」「育児休業取得後の継続勤務」「所定外労働の削減」「多様な労働条件の整備」など、仕事と家庭の両立における対策や実施状況が優良であり、より厳しい基準を満たした企業のみが厚生労働大臣から受けることのできる認定。
※3:法律上、育児休業制度は「子供が1歳になるまでの間、特別な事情がある場合は2歳まで」取得できるが、サンドラッグでは、入社2年以上の正社員は「特別な事情がある場合は子供が3歳まで延長して休業」することができる。
※4:法律上、育児短時間勤務制度は「子供が3歳の誕生日を迎えるまで(努力目標として小学校の入学式の前日まで)、勤務時間を6時間に短縮できる」となっているが、サンドラッグでは「特別な事情がある場合は小学校6年生終了まで勤務時間を6時間に短縮できる」となっている。
※5出典: 東京都 「令和5年度東京都男女雇用平等参画状況調査」





 クローガーが予測「25年の5大フードトレンド」、セインズベリーのアルディ対策とは
クローガーが予測「25年の5大フードトレンド」、セインズベリーのアルディ対策とは