テクノロジーに振り回されずに「正しいDX」を実践する方法とは
内製化を推進する大手、中小チェーンの打ち手は?
すでに先進的な小売業は、IT人材を自社で抱える、いわゆる「内製化」によってDXを推し進めている。
食品スーパーのベイシア(群馬県/相木孝仁社長)、ホームセンターのカインズ(埼玉県/高家正行社長)、作業服チェーンのワークマン(東京都/小濱英之社長)などを抱えるベイシアグループでは、グループ横断でDXを推進する戦略子会社ベイシアグループソリューションズ(群馬県)を22年9月に設立。IBM出身の樋口正也氏が旗振り役となり、DXを急加速させている。家電小売業大手のビックカメラ(東京都/秋保徹社長)も、22年6月に「DX宣言」を発表。同9月にIT子会社ビックデジタルファーム(東京都)を設立し、エンジニアの採用を強化中だ。
特集内では、ベイシアグループソリューションズ社長の樋口氏、ビックカメラ執行役員デジタル戦略部長 兼 ビックデジタルファーム社長の野原昌崇氏へのインタビュー取材も実施している。大手小売が明確なビジョンを持って戦略的にDXを推進していることがわかるはずだ。
ただ、内製化によるDXはIT人材の人件費をはじめコストの問題から、すべての企業が取り組めるわけではない。とくに、寡占化が進んでいない食品スーパーなどの業態は中小・中堅チェーンが多く、投資できる体力も限られる。そうした企業がDXを推進していくには、その前の段階で、自社の戦略、変革後の姿を明確化し、そのために必要なデジタルは何なのかを理解・整理しておくことが重要になる。
そのためには経営者が自ら勉強して理解するか、経営戦略とその実現に必要なデジタル施策を結びつけ、外部とのやりとりで的確な要件定義ができる人材が必要であることはいうまでもない。これができないままベンダーと付き合い続けた場合、ムダな投資をし続けることになる。
そしてその際、外部ベンダーとの協業しか選択肢がないのかというと、そういうわけでもなさそうだ。顧客時間の共同CEO取締役の奥谷孝司氏は「DXにおいては、『顧客体験』と『カスタマーサクセス』を考える必要がある」としたうえで、「カスタマーサクセスは、身近にあるテクノロジーでも十分に実現可能」と説く。
たとえば、スマートフォンは高性能なカメラが標準装備となっており、ビデオ通話もできる。そうした機能をうまく使えば、顧客を満足させることは十分可能だというのだ。実際に、ロケスタ代表の長谷川秀樹氏がCIO(最高情報責任者)を務める生活協同組合コープさっぽろ(北海道/大見英明理事長)では、目視で行っていたチェック業務を、スマートフォンで撮影した画像を使って遠隔で行うなどの業務改善を行っている。長谷川氏は「企業の経営や現場の業務にきちんと寄り添い、目的を最速で実現するために、デジタルを使ってどうするかを主軸として、実現可能なことからどんどん実行していくほうが望ましい」と話す。
DXを検討するうえでは、「自社のDXには本当に高度なテクノロジーが必要なのか」という視点も忘れないでおきたいところだ。
「勝つDX」の本質 の新着記事
-
2023/03/31
メアドなしから日本有数のDX企業へ グッデイ柳瀬隆志社長が実践するDX成功のための方法とは -
2023/03/31
カインズも導入、小売業界に導入進む、最新技術の知能ロボットとは? -
2023/03/31
リテールメディア勃興で遅れていた日本の小売のDXが動き出す!データ活用の課題と手法は? -
2023/03/30
自動発注シェア1位のシノプス、総菜にも対応したAI活用のシステムとは -
2023/03/30
意外!?データ活用で学ぶべきはコスモス薬品である当然の理由とやり方 -
2023/03/30
壮大な物流DXを進めるアルペンが国内トップレベルの生産性を実現できた理由
この特集の一覧はこちら [15記事]

関連記事ランキング
- 2023-04-048期ぶり黒字転換、経営破綻からビジョンメガネが復活できた理由
- 2023-03-27データ分析で商品企画まで変える!樋口正也氏が語るベイシアグループのDX戦略とは
- 2023-03-281号店から3年、進化する無人決済店舗TOUCH TO GOの現在地
- 2023-03-30意外!?データ活用で学ぶべきはコスモス薬品である当然の理由とやり方
- 2023-03-30壮大な物流DXを進めるアルペンが国内トップレベルの生産性を実現できた理由
- 2023-03-31リテールメディア勃興で遅れていた日本の小売のDXが動き出す!データ活用の課題と手法は?
- 2023-04-01青果売場2023年春夏の売場づくりのカギとシーズン販売計画書の作り方
- 2023-04-04「大総菜プロジェクト」を最大規模で体現するサミットストア川口青木店の売場づくりを徹底解説
- 2023-04-07欧米で広がる新業態「ドライブアップ・グロサリーストア」の衝撃とは




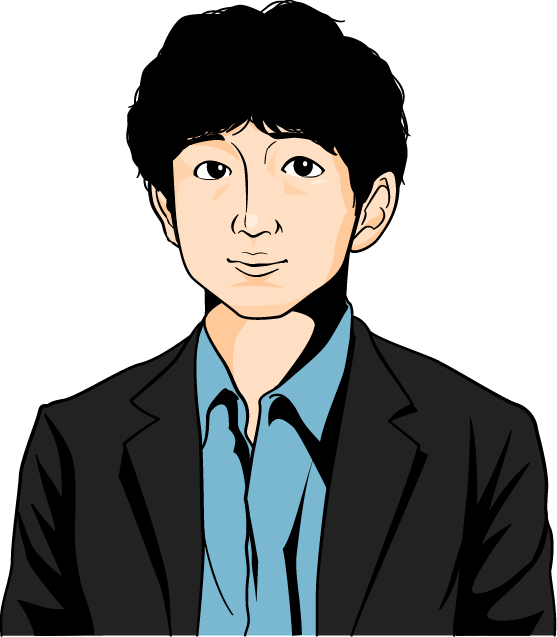
 前の記事
前の記事