値上げ時代、スーパーマーケットが取るべき価格戦略とそのための仕組みづくりとは何か?
同業他社との連携も進む
最近では、作業の効率化や生産性向上を図るため、グループ内外の企業と協業する動きもみられるようになった。
まず挙げられるのが、商品の仕入れにおける協業である。一括で大量に仕入れることができれば、それだけ原価を低減することが可能だ。以前からディスカウントストア(DS)などは品揃えを絞り込み、単品を大量に売り込む戦略を採っているが、最近ではSMでもグループ内外との連携を強め、仕入れ数量を増やしている。
中部地方を中心にSMを展開するバロー(岐阜県/森克幸社長)は、中部薬品(同/高巢基彦社長)やホームセンターバロー(同/和賀登盛作社長)といったグループ内の他業態と連携するほか、アークス(北海道/横山清社長)やリテールパートナーズ(山口県/田中康男社長)と結成した「新日本スーパーマーケット同盟」での取り組みの一環として共同で商品を仕入れ、売場で大量展開し徹底的に売り込んでいる。グループ内連携では、月間の単品販売数量が日本一となる商品も出ており、同盟での取り組みでは、3カ年で約12億円の原価低減に成功している。

他社との連携による取り組みは、物流の領域にも及び始めている。イオン九州(福岡県/柴田祐司社長)は22年8月、トライアルホールディングス(同/亀田晃一社長:以下、トライアル)をはじめ、九州を地盤とする小売企業13社とともに、企業横断型で「物流の2024年問題」や脱炭素といった課題に対処し、持続可能な物流の実現をめざす「九州物流研究会」を発足した。すでにイオン九州とトライアルの福岡県内の店舗で共同配送の実験が始まっている。
値上げ時代の新価格戦略! の新着記事
-
2022/11/14
生鮮を安く売るマミーマート の生鮮市場TOPの価格戦略と売場づくりを徹底分析! -
2022/11/14
ヤオコーのDS、フーコットに見られた「進化」と客層拡大の理由とは -
2022/11/11
ディスカウンティングフォーマットのつくり方と成功の決め手 -
2022/11/11
激安総菜とPBに強み 値上げ時代に集客力高める大黒天物産の強さの秘密とは -
2022/11/10
店内作業30%削減に食用油高騰への秘策も…平和堂の「EDLC」政策とは -
2022/11/10
イトーヨーカ堂、グループを挙げた製造体制の強化でめざす「低価格づくり」とは
この特集の一覧はこちら [10記事]
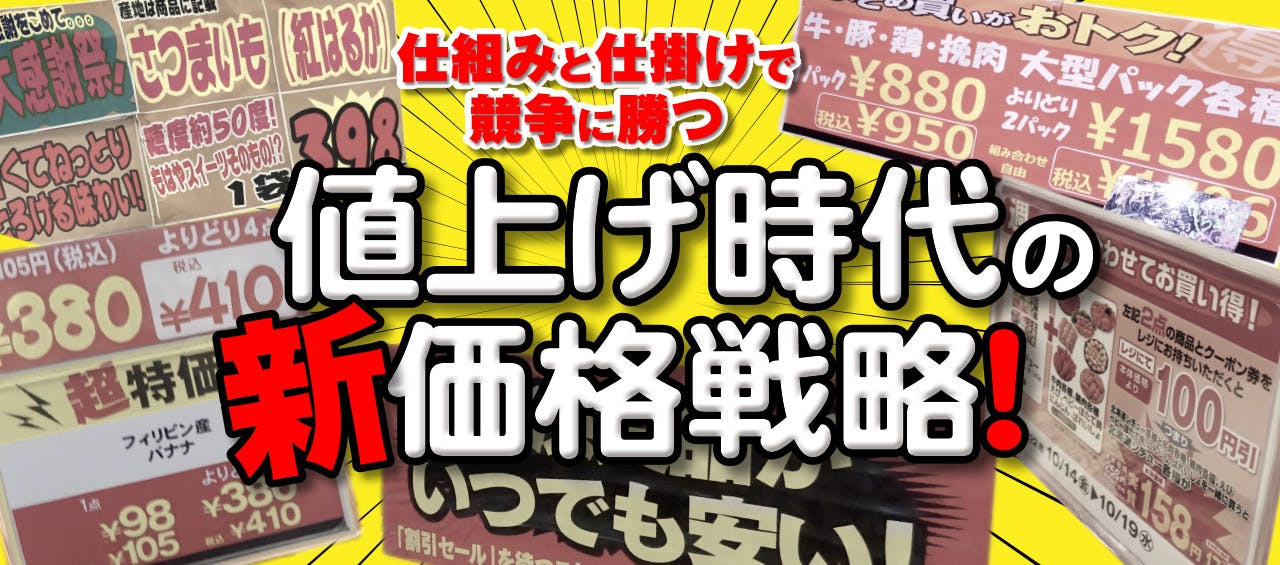
関連記事ランキング
- 2025-11-21速報!バロー関東1号店「横浜下永谷店」 オープン日の模様を徹底レポート
- 2025-11-21ベルクのディスカウントフォーマット「クルベ」、開店から2年超で見えた変化と進化
- 2025-11-26気づけば5店舗……クスリのアオキが出店増やす「スーパーのアオキ」の全容
- 2025-11-19上期絶好調のバローHD 関東進出直前、小池社長が明かした「攻め手」
- 2025-11-25オープンから2年超のクルベ その至近で競合するヤオコー、2店舗の関係から見えてきたこと
- 2025-11-21楽天撤退、ライフ参入 センター型ネットスーパー激動期へ
- 2025-11-17利益面に明暗……ライフ、U.S.M.H、アークスの中間決算を解説
- 2025-11-12ロピア進出機に阪神エリア随一の激戦地に 兵庫・尼崎エリア視察案内!
- 2025-11-22圧倒的集客力で激戦地を制圧!? 茨城タイヨーの「ビッグハウス」を大解剖!
- 2025-11-11意外にも”共存共栄”? 関西随一の激戦区・西宮の2エリアを徹底視察!
関連キーワードの記事を探す
気づけば5店舗……クスリのアオキが出店増やす「スーパーのアオキ」の全容
「ドラモリ」が価格競争の台風の目に? フード&ドラッグ激戦区・宮城県名取市を現地調査





 前の記事
前の記事