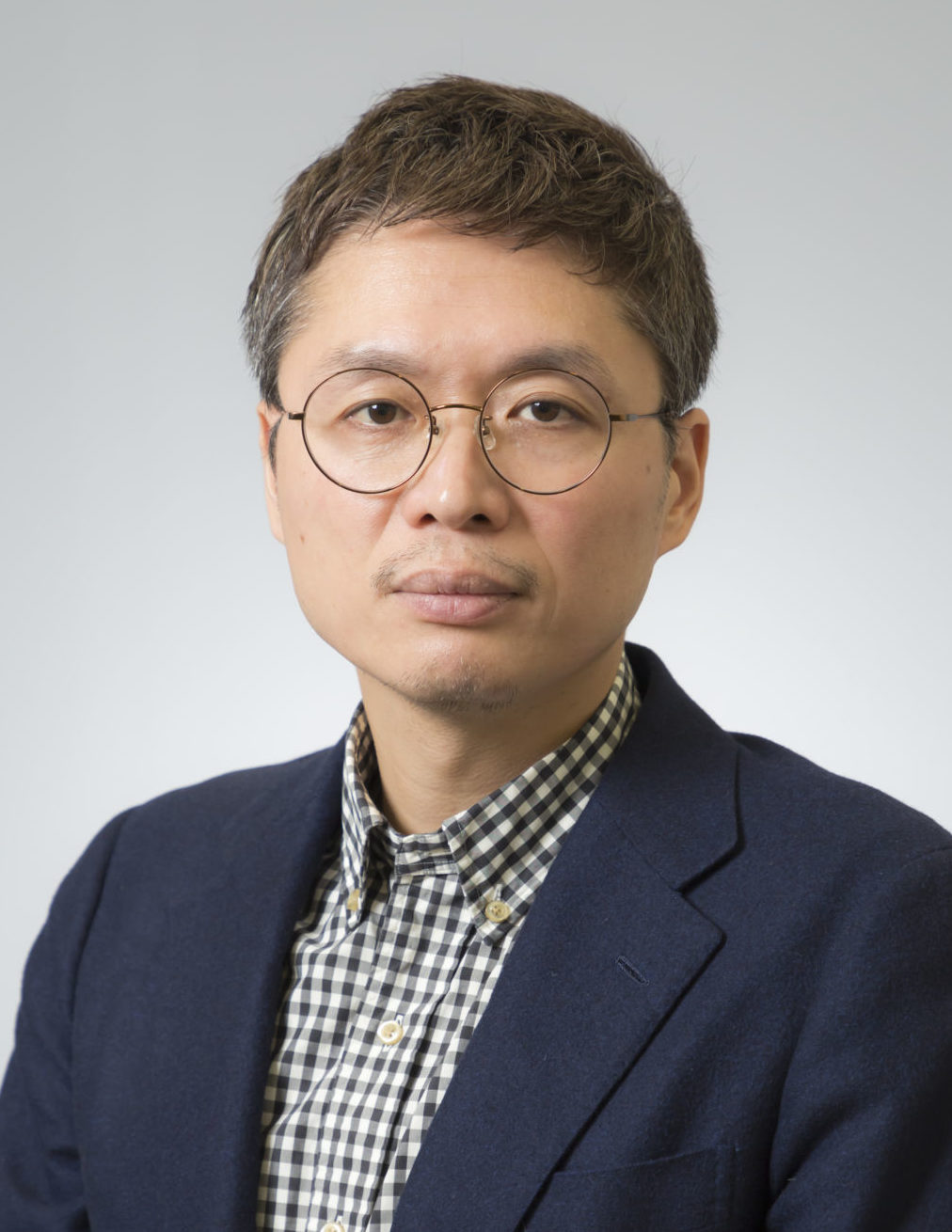顧客時間・奥谷孝司氏、「DXとはお客と一生つながり続ける覚悟を持つこと」の真意とは
流通小売業界では近年、先進的な技術力、あるいは独自性あふれるビジネスモデルを武器に活躍する企業が続々と登場している。そうした注目流通関連企業の経営トップに、小売の魅力、小売業界の今後の展望を語っていただく本連載。第2回は、顧客時間の共同CEO取締役の奥谷孝司氏に話を聞いた。

デジタルに取り組む「覚悟」とは
──小売業界に興味を持ったきっかけと、小売業の魅力からお願いします。
奥谷 私のキャリアは人材派遣業の営業から始まりました。小売は自分にとって一番身近でわかりやすい業界だと思い転職しました。
作って、仕込んで、売る──シンプルですが、これこそが小売業の難しさであり、魅力であると思います。これからの時代は、作って、仕込んで、売ることの精度を上げていかなければ勝てない時代がやってきます。そうすることで、よりエコなものづくりができると思います。
共同CEOを務める顧客時間で企業のDX(デジタル・トランスフォーメーション)のお手伝いする際は、クライアント企業に「DXはお客さまと一生繋がり続けるという覚悟を持つということだ」と言っています。お客さまと向き合う覚悟があるからこそ、デジタルに取り組める。そういった覚悟が身につくところも、小売業の魅力だと思います。
──顧客時間を立ち上げた経緯をお教えください。
奥谷 2018年に「世界最先端のマーケティング」(日経BP)を執筆した当時、共同執筆者だった岩井(岩井琢磨氏・顧客時間共同CEO)君が、「一緒に会社をやりませんか」と言ってくれたのがきっかけです。
オイシックス(現オイシックス・ラ・大地)に入社した頃から、私はパラレルキャリアを志向していました。当時は、世の中に「デジタルを通してお客さまに繋がりたい」と考える企業が増えてきた頃で、「そこを応援しなくては日本の小売業や企業全体もデジタル化への対応が進まない」と考えていました。
ECを例にとると、ECを「電子商取引」ではなく、「顧客と繋がり続けるエンゲージメントコマース」として活用する。小売業のそうした取り組みを応援していきたいという思いから、会社を立ち上げました。
顧客時間の事業は、アプリ開発やECリニューアルだけでなく、D2Cブランドづくりの応援や顧客データを活用したデータビジネスなど多岐にわたります。「クライアントがお客さまと繋がる覚悟を身につけてもらうことを支援する」というのが当社の役割であると考えています。
「小売業の取り組みは、社会のデジタル化にも役立つ」
──オイシックス入社時からパラレルキャリアを描かれていたということですが、どのようなきっかけでそう考えるようになったのでしょうか。
奥谷 元々は博士課程で学び直したいという思いがありました。私の話、あるいは執筆したものが社会の役に立つのであれば、所属企業に気を使うことなく本腰を入れてやりたいと考えていました。
自分の視座が上がっていく中で、DXを通した人との繋がりの重要性を再認識し、「小売業が今取り組んでいることは、社会のデジタル化にも非常に役立つ」という実感を得ました。
実際に顧客時間を18年に設立して以来、一気にさまざまな会社の支援が始まっていきました。結果論になりますが、自分なりに時代の先を行き、挑戦して失敗したことの積み重ねが現在に生きていると実感しています。
──顧客時間の直近の取り組みについて教えてください。
奥谷 三井住友カードの「Custella(カステラ)」というキャッシュレスデータを活用したデータ分析支援サービスがあります。同サービスを使って、顧客時間では2020年5月からコロナ禍での消費行動の変化をまとめた「コロナ影響下の消費行動レポート」を複数回にわたり発表しています。
また、ホームセンター大手のカインズが19年から推進する「DIYer100万人プロジェクト」において、ワークショップの開催、事業強化設計、顧客接点・メディア開発など顧客体験全体を作成する支援も行いました。
そのほか、オリンパスのECサイトのリニューアルもお手伝いさせてもらいました。実は顧客時間にはエンジニアはいませんが、「デジタルでやれること」「店舗でやれること」をそれぞれ解釈したうえで、システム担当者に渡すRFP(提案依頼書)やRFI(情報提供依頼書)などを作成するサポートをしました。