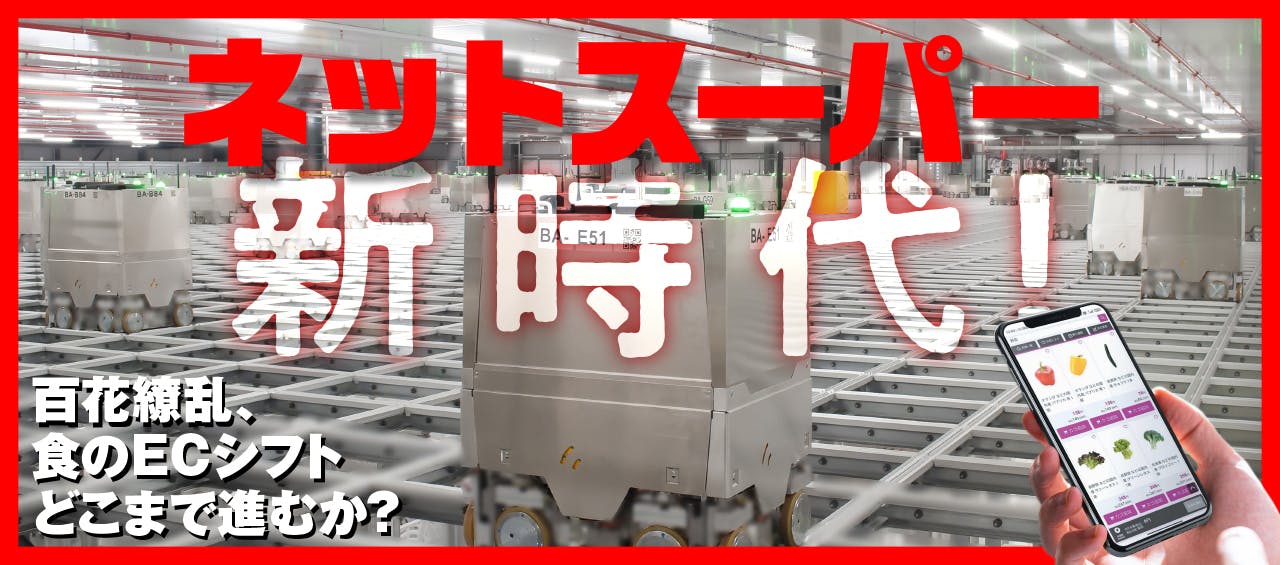
コンビニエンスストア大手のローソン(東京都)、海外法人の代表、ニトリホールディングス(北海道)、傘下の物流企業ホームロジスティクス(東京都)社長、SBロジスティクス(同)のchairmanなど、各社で経営やマーケティング・サプライチェーン改革の重責を担ってきたNice Ezeの松浦学氏。同氏は、食品小売業各社がネットスーパー事業に参入する前に、自社のサプライチェーン、そして現在の事業環境を今一度見つめ直す必要性を説く。その理由を解説してもらった。
店舗事業の物流のムダをなくすことが先決
現在、食品小売業界では、ネットスーパー市場を次なる成長源にしようと新たな物流整備を進めている。
ここで押さえておきたいのは、ネットスーパー事業は店舗事業と商品を売るまでのモノの流れが大きく異なり、物流負担が大きいことだ。店舗物流は、ある程度大きなロットのまま、物流センターから各店舗に商品を運び、店舗の従業員が売場に並べれば完了だ。そこから先は来店客がセルフサービスで購入していく。
一方のネットスーパー事業の場合は、受注、商品のピッキング、梱包、個宅配送まで行う。多くのプロセスとコストが必要であり、個々の作業は一人ひとりの注文に沿って行う必要があるため複雑かつスピードも求められるのだ。
こうしたなか食品スーパー(SM)を中心に多くの食品小売業では、比較的単純である店舗事業の物流においても、いまだ多くのムリ・ムダ・ムラがみられる。複雑なネットスーパー事業に着手する以前に、まずは既存の物流、そしてサプライチェーンそのものを今一度見直すべきだと考える。
たとえば、物流センターから店舗までの商品配送において、毎週決まった曜日・時間・回数など、従来どおりの方法で納品をしている体制だ。次回の配送でも間に合う店舗や商品でも、わざわざ車両を手配して低い積載率で納品する例や、開店前の納品にこだわっている企業が多い。輸送力不足が解消されない時代にもかかわらずだ。店舗や商品の優先度をあらためて格付けし、抜本的に見直すことが必要だろう。
いまや、データで日々の需要予測から発注の自働化までしている企業もあるが、それらはサプライチェーン改革にまで昇華させてこそ大きな果実を得られるのだ。しかし、いまだにサプライチェーンの各プロセスの関係性やコストが把握されていない、または全店一律の物流経費率で店舗損益を管理している企業すらあるのが現実だ。プライベートブランド商品の開発においては、具体的な仕様書もなく、調達や製造工程にもかかわっておらず、実質利益をとらえていない。これでは海外の小売業を何度視察しても、デジタル化をしても、経営の高度化には到底至らない。
中国や米国とは異なる日本の事業環境
ネットスーパー事業については、一度立ち止まって考えるべきだ。
新型コロナウイルス感染拡大で、ECの利用は拡大した。非接触で時短にもなるため、EC化率30%超えの中国や約15%の米国のように買物のECシフトが進むといわれている。それに応じて、現在3%程度にとどまっている国内の食品EC化率も高まるはずだという見方からネットスーパー事業への投資が加速しているのだが、この点には疑問がある。というのは、日本と中国や米国では、社会環境が大きく違っているからだ。
中国や米国では都市化率(都市部に住んでいる人口の割合)は6割程度にとどまり、店舗密度も低いなどECの利便性は高い。また、食品ブランドも小売企業も寡占化率が高いことも一因だ。
それに対して日本の場合、都市化率は9割と高く、人口密度も高い。徒歩圏内にはSM、コンビニエンスストア(CVS)、ドラッグストア(DgS)などの生活基盤を満たす店舗が高密度、しかもQSC(品質・サービス・清潔さ)の高いレベルで存在している。こうした環境にあって、
・・・この記事は有料会員向けです。続きをご覧の方はこちらのリンクからログインの上閲覧ください。